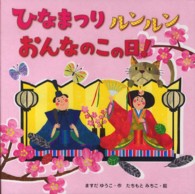内容説明
『東海道四谷怪談』で、お岩の幽霊は燃える提灯からさかさまの姿で現れる。なぜ“さかさま”なのか。この恐怖の演出には、じつは根源的な必然性があった―“さかさま”という逆転の構図の背後に横たわる精神史に迫った「さかさまの幽霊」。世の中を“まさま”と“さかさま”との関係において見据え、幕末転換期の江戸の真実をリアルに切り取った鶴屋南北の世界を鮮やかに分析する「南北劇の構図」。芸能のさまざまな図像から、江戸庶民の意識と欲望、時代のエネルギーをスリリングに読み解く、歌舞伎のイコノロジー。文庫化にあたり、「河鍋暁斎の発想と表現」「図像の創成」の二編を増補。
目次
1 歌舞伎のイコノロジー(南北劇の構図―“逆転”“混淆”の哄笑と恐怖;さかさまの幽霊;象引―芝居と絵画;和合神の図像)
2 歌舞伎の色彩論(辺界の色―黒の造型;赤のシンボリズム)
3 都市の中の芸能空間(四条河原の芸能と見世物;芝居と見世物のある風景)
補論(河鍋暁斎の発想と表現―対極・混淆・逆転の構図;図像の創成―貧乏神と和合神)
著者等紹介
服部幸雄[ハットリユキオ]
1932年生まれ。名古屋大学文学部卒業。歌舞伎研究、日本芸能文化論専攻。国立劇場芸能調査室主任専門員、千葉大学教授、日本女子大学教授を経て、千葉大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
36
歌舞伎を主軸に『東海道四谷怪談』でのお岩さんはなぜ、さかさまになって現れるのかという意味、歌舞伎での黒や赤の色彩の意味、和合神の変化とその思想背景など、ビジュアルを対象に江戸の文化やその背景を論じた本。ゼミの期末レポートで知りたかったことはちょろっとしか触れていませんでしたが、中々、興味深かったです。2014/01/14
たっきー
2
歌舞伎研究の大御所の名著。幽霊をさかさまに描くことで異常を表すというのが趣旨。確かに近世の幽霊は逆立ちして描かれているものがある。異常性を表現する一つの手法だったことは間違いない。2005/01/01
いちはじめ
2
絵画などの図像をヒントに読み解く江戸歌舞伎論/文化論。なかなかスリリングな論考。文庫化に際して増補された河鍋暁斎論も面白い2005/01/16
-

- 電子書籍
- ハニカミの島~女だけの島と淫らなナラワ…
-
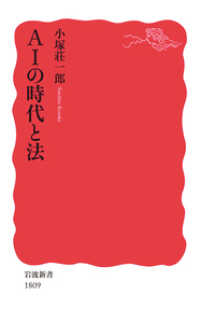
- 和書
- AIの時代と法 岩波新書