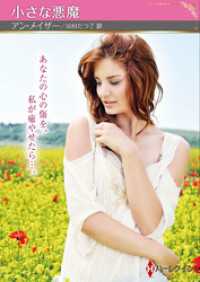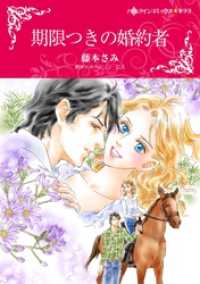内容説明
いざ、いじめが起きたとき―組織的・適時適切な“対応”が子どもを救う!研究者+現職校長+第三者委員会委員長、3つの立場で経験豊富な著者が明快解説。
目次
基本編 「いじめに対応できる学校」とは?(いじめ防止対策推進法施行後のいじめ防止対策とは;最新のいじめを理解する五つのキーワード;深刻ないじめを生じさせない学校運営;いじめ重大事態にどう対応するか)
実践編 いじめCase Study(いじめ防止の局面;いじめ認知の局面;いじめへの対処の局面;重大事態の局面)
著者等紹介
藤川大祐[フジカワダイスケ]
千葉大学教育学部教授(教育方法学、授業実践開発)。1965年東京生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得満期退学。金城学院大学助教授、千葉大学准教授等を経て、2010年より現職。千葉大学教育学部附属中学校長及び千葉大学教育学部副学部長を併任。メディアリテラシー教育、数学教育、キャリア教育、道徳教育等、教科・領域を超えた新しい授業実践や教材の開発に取り組むとともに、いじめ・学級経営についても研究。千葉市教育委員、内閣府「子供・若者育成支援推進のための有識者会議」構成員、NPO法人企業教育研究会理事長、NPO法人全国教室ディベート連盟理事長等を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
saiikitogohu
1
「一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身に苦痛を感じているもの」「個々の教職員が、把握された事態が「いじめ」に該当するかどうかを判断する必要はありません。まずは児童生徒が苦痛を覚えた可能性があることについて共有し、…必要な支援をすることを考えることが求められる…教職員が直接捉えられることができるのは、法律上の「いじめ」ではなく、児童生徒が苦痛を覚えている様子…「いじめを認知したら報告」でなく、「苦痛を覚えた可能性」を報告」162021/12/18
ジョルジオ鈴木
0
★★★★ 最新事例をあって良い。2021/07/28