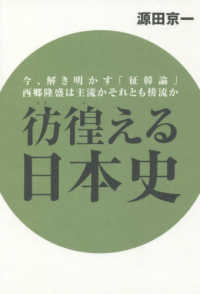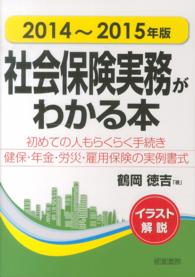目次
第1章 政治を問う
第2章 国際関係を観る
第3章 道徳を学ぶ
第4章 社交を察する
第5章 「生きる」を考える
第6章 歴史を想う
第7章 哲学を思う
第8章 実利を計る
著者等紹介
西部邁[ニシベススム]
1939年、北海道に生まれる。東京大学経済学部を卒業する。東京大学教養学部教授を経て、評論家として活動。政治・経済・社会・文化と幅広い分野にわたって健筆を揮い、講演活動を行う。月刊言論誌『発言者』主幹であり、秀明大学学頭でもある。『経済倫理学序説』(中央公論社)で吉野作造賞、『生まじめな戯れ』(筑摩書房)でサントリー学芸賞受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
姉勤
39
119の社会、政治、人物、哲学に関する設問に答える。スペシャリストではなくジェネラリストとして。途方もない長い時間、多くの人々によって取捨選択,デバッグ,安全装置を設けられてきた、歴史と伝統という物差しを持って、古典を使って世界をみる。見た後に、世に正義正解として溢れているものの、矛盾,欺瞞,瑕疵。所詮人間、現代が変化、高度化しているわけでなく、使う道具が扱いかねるほど急激に進化しているにすぎない。その道具の奴隷か同化する諦観、ニヒリズムに傾くことなく、人間が人間を取り戻すか否かを任せて、著者は本年入水。2018/02/10
Kooheysan
6
20年ぶりに再読しました(初版2004年)。あの当時と比べて、わかるところが増えた気がして成長を感じました。よくよく読んでみると、かなりバランスの取れた記述が多い印象です。多少物の見方が変わった自分にも、考えさせることが多く、実りの多い読書となりました。それにしても、これほどに広く深く語れるというのはジェネラリスト(専門人ではない、本当の意味の知識人)としての西部邁氏の面目躍如といったところでしょう。2025/05/22
station to station
3
本書の題である「学問」とは、専門化・単純化した知識や理論のことではない。真の意味での「学問」とは、物事の全体像をつかむための総合的な知のあり方を指し、それを引き受ける者を著者は「ジェネラリスト」と呼び、現代は専門人(スペシャリスト)たちがジェネラリストを扼殺する時代であるという。政治や国際関係から人間論、死生論、さらには人物評に至るまで縦横無尽に論じる本書は、「ジェネラリスト」としての著者の面目躍如である。2020/05/30
今川栄吾郎
2
政治・国際関係・道徳・社交・生きる・歴史・哲学・実利という8分野に大きく大別された構成になっている。 各項目を通じて西部さんが言いたいことを無知な私なりに簡潔に述べると、近代になって日本が失ってしまった事柄を指摘し「保守の神髄の提示」、思想対立に代表されるようなどちらか極端ではなく「平衡」であることの大切さ、現代の所謂専門家と言われる人の「専門家」であるが故の視野の狭さ、またそれに迎合している「大衆」が作り出す社会への危機への警告これがざっくとした私なりの解釈です。 また、再読したい本です。2018/05/14
有無
2
西部さんの言いたいことをダイジェストで詰めたような本。現在を漫然と生きている人に、一滴の懐疑を与える本。2011/01/19
-

- 電子書籍
- 断罪された悪役令嬢の次の人生はヒロイン…
-

- 電子書籍
- 真祖がバカなら眷属も。【分冊版】 24…