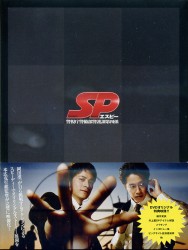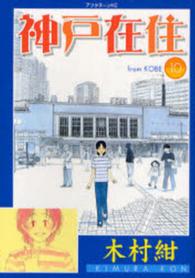出版社内容情報
カンボジアを中心にタイ、ラオス、ビルマ、ベトナム、インドネシアの遺跡、彫像、彫刻の歴史的意義と美術的価値を詳しく紹介。カラー口絵37ページ、本文中の写真300点満載。長らく翻訳が待たれていた名著の完訳です。本格的な解説書の刊行は初めてです。
目次
第1章 インドシナ
第2章 初期アンコール美術
第3章 アンコール古典期
第4章 チャンパ
第5章 シャムとラオス
第6賞 ビルマ
フィリップ・ローソン著『東南アジアの美術』と私との出会いは1987年にさかのぼる。夫の転勤地スリランカからバンコクへ戻った私は、バンコク国立博物館ボランティアの仲間たちと美術の勉強をしていた。ボランティア活動の主体はバンコク国立博物館内でのガイドであったが、歴史と美術に関するスタディーグループも盛んであった。
そんな時、運命に導かれたというか、ある時にふと手に取った本がローソンの『東南アジアの美術』であった。著者の名に馴染みはなかった。東南アジアあるいはインドシナ専門家として、文献目録でフィリップ・ローソンの名を見たことはなかった。いわば「通俗的」な顔で街の書店に並んでいた本を、内容にあまり期待はしていないで読みはじめたのであったが・・・・・面白かったのである。おりしも勉強会が計画されていたクメール美術の章から読み始めた私は、たちまちローソン氏の虜になってしまったのである。
ローソン氏に導かれるままに、プレ・アンコール期の巨大石像の「官能的な面のひろがり」を追い、その正面性に魅せられた頃、私はクメ-ル彫像を「観る」戸口に立っていたのであろう。しかし、カンボジアはまだ「近いが、遠い国」であった。憧れの古
東南アジアの遺跡、美術品の超豪華な解説書です。カンボジアを中心にタイ、ラオス、ビルマ、ベトナム、インドネシアの主要な遺跡と彫刻・彫像の歴史的意義と美術的な価値を詳しく説明。長年翻訳が待たれていた名著の完訳です。写真300枚。冒頭に32ページのカラー写真による口絵を付けました。
内容説明
本書では、西欧に蓄積された知識の系譜に沿って、1960年代の現地ナショナリズムと西欧の野心の磁場であった「東南アジア」を美術フロンティアとして指し示し、その美を鑑賞するロードマップが描かれている。
目次
第1章 インドシナ
第2章 初期アンコール美術
第3章 アンコール古典期
第4章 チャンパ
第5章 シャムとラオス
第6章 ビルマ
第7章 ジャワとバリ
著者等紹介
ローソン,フィリップ[ローソン,フィリップ][Rawson,Philip]
1924‐95年。第二次大戦後の英米国で活躍した美術学者。未開の地の美術からインド、中国、チベット、そして東南アジアにいたる広い地域の美術や宗教に関する啓蒙的な講義を行ない、著作を残した。博物館学芸員のキャリヤも長く、ダーラム大学グルベンキアン東洋美術博物館の副学芸員、オックスフォードで極上の美術品を所蔵することで有名なアシュモリアン博物館アジア美術部副館長等をつとめた
レヌカー・M[レヌカーM]
本名・秋山良子。1940年生まれ。1963年国際基督教大学教養学部社会学科卒。東京都立大学社会学科修士課程(社会人類学専攻)、在学中にインド奨学金によりデリー大学留学。立教大学文学部史学科博士課程終了(地理専攻)。1971年タイに居住する。1972年バンコク国立博物館ボランティアガイド日本語グループを創設。現在、「レヌカーの旅」を主催するレヌカー&カンパニー社を経営している
永井文[ナガイアヤ]
1954年生まれ。1979年東京工業大学大学院修士課程終了(電子科学専攻)。1987年タイに渡る。バンコク国立博物館ボランティアガイド日本語グループ17期として活動。1993年帰国。1996~1999年タイに渡り、バンコク国立博物館ボランティアガイド日本語グループに再び参加
白川厚子[シラカワアツコ]
1954年生まれ。1976年大阪大学人間科学部卒。1987~90年アラブ首長国連邦アブダビ在住。湾岸戦争のため帰国。1996~2001年タイ、バンコクに暮らす。バンコク国立博物館ボランティアガイド日本語グループに25期として活動。2001年日本に帰国
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。