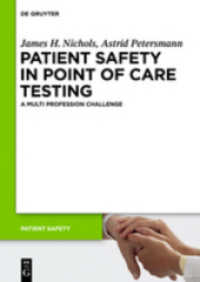- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
日本人の嗜好品がどう変化したかがわかる本。
いまやタバコもコーヒーも嗜好品ではない? 日本人は「楽しみ」や「安らぎ」のために何を買うのか。嗜好品の変遷を描く新しい文化論。
ミネラルウォーターの値段は水道水の1700倍。ところが、生産量はわずか20年で1万倍にも増えている。これほどのヒット商品は少ないし、いまやミネラルウォーターは酒・タバコ・コーヒーといった従来の嗜好品と同様の存在になったといっていいだろう。そう考えると、消費者にとって「なくてはならないもの」「心の満足をもたらすもの」が売れる商品ではないか。その仮定のもと、さまざまな年代の男女に聞き取り調査をしながら、現代における嗜好品とは何かを探ったのが本書である。調査の結果、わかってきたのは、携帯電話や化粧品もいまや嗜好品に含まれるかもしれないという「文化の変容」であった。もともと「嗜好品」とは日本語特有の言葉だが、それをキーワードに新しいマーケティングの手法を試みた本書には、日本人が求めているもの、関心のあること、これから欲しいものが浮き彫りにされている。消費者のニーズをつかみたい人には必読の書である。
●第1章 嗜好品が開く「楽しみの時代」
●第2章 「楽しむ」という価値の発見に向けて
●第3章 現代日本人の楽しみと嗜好品
●第4章 嗜好品としての清涼飲料水とその市場
●第5章 嗜好品世界の広がりと多様性
●第6章 情報社会で嗜好品が果たす役割
●終章 「相互ケアの時代」と嗜好品―総合討論
内容説明
「嗜好品」という日本語特有のキーワードから新しいマーケティングの手法を探った注目の書。
目次
第1章 嗜好品が開く「楽しみの時代」
第2章 「楽しむ」という価値の発見に向けて
第3章 現代日本人の楽しみと嗜好品
第4章 嗜好品としての清涼飲料水とその市場
第5章 嗜好品世界の広がりと多様性
第6章 情報社会で嗜好品が果たす役割
終章 「相互ケアの時代」と嗜好品―総合討論
付録―研究会メンバーの「嗜好品文化研究」への思い
著者等紹介
高田公理[タカダマサトシ]
1944年、京都生まれ。1968年、京都大学理学部卒業後、酒場経営、コピーライター、広告制作業経営、シンクタンク研究員、愛知学泉大学教授を経て、1992年より武庫川女子大学教授。専攻は情報文明学、観光文明学。最近は、旅と観光、食文化、酒やたばこなどの嗜好品、眠りなど、人生の多様な「楽しみ」を研究課題にしている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
B.J.
まつい