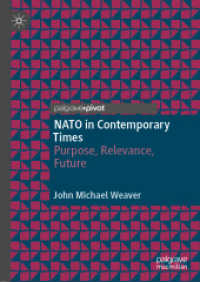目次
第1章 地上の視点、神の視点(「対話の場」と日本人;「アイ・ラブ・ユー」を日本語でどう言うか ほか)
第2章 「あげる」と「くれる」は敬語だった(「あげる」と「くれる」はどう違う;「やり・もらい」と太陽の動き ほか)
第3章 戦後の敬語の大変化(敬語はどう評価されているか;敬語はどう変わってきたか ほか)
第4章 語源で敬語に強くなる(謙譲語も実は尊敬語;主体尊敬に隠れた「ある」 ほか)
第5章 俳句と相撲と庭園と(「古池や蛙飛び込む水の音」は何を詠ったのか;俳号と四股名に見る「自然崇拝」 ほか)
著者等紹介
金谷武洋[カナヤタケヒロ]
1951年北海道生まれ。函館ラ・サール高校、東京大学教養学部卒業。ラヴァル大学で修士号(言語学)、モントリオール大学で博士号(言語学)取得。専門は類型論、日本語教育。カナダ放送協会国際局などを経て、現在、モントリオール大学東アジア研究所日本語科科長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
KAKAPO
21
「自我を切り離す西洋人」と「自我をつなぐ日本人」西洋の〈話し手〉は〈聞き手〉と切れているのに対して、日本語では両者がつながり、同じ方向を向いて視線を溶け合わすと言える。「他と区別し自立したものとして形成されている西洋人の自我は日本人にとって脅威。日本人は他との一体的なつながりを前提とし、それを切ることなく自我を形成する。非常に抽象的に言えば、西洋の自我は『切断』する力が強く、何かにつけて明確に区別し分離してゆくのに対して、日本人の自我はできるだけ『切断』せず『包含』することに耐える強さをもつといえる。」 2013/12/22
壱萬弐仟縁
11
師匠と弟子。敬語は、日本人誰もが相手を高めて自分を下げる、謙譲の文化を築いてきた。しかし、敬語を正しく使える人も徐々に減ってきたと思われる。英語との、フランス語との違いなども指摘されながら、日本語の特徴に言及される。48ページには鈴木孝夫先生の説明も引用。日本語の敬語は思いやりの言語なのかもしれない。礼儀正しさ。ヨコ敬語はシーソーだという(102ページ)。市民のフラット目線のようで好感。2013/06/13
phmchb
4
( ..)φメモメモ『暮らしの中の敬語』伊吹一/笠間選書(1975)、『敬語表現』蒲谷宏・川口義一・坂本恵/大修館書店(1998)2019/01/30
Noelle
4
言語を手がかりとした日本と西欧的な世界観、引いては比較文化論的な内容で とてもうなずける展開だった。敬語のあり様が、「挙げる、くれる」という縦方向の位置関係によること、また視点の置き場所が地上にある日本と、上空にある西欧との、俳句・相撲・庭園などを例にとった比較が 我々日本人の心性の基盤になってるものの理解を非常に深めてくれる。「言語は話者の世界観をかえる」、主語 I が大文字で書かれる唯一の言語である英語と 二人称の親称・敬称のあるフランス語・ドイツ語との違いなども なるほど な感じです。2013/12/09
みそさざえ
3
敬語をもとにした日本文化論。英語の上からの視点と日本語の地上の視点の対比がおもしろい。語幹のローマ字分析は説得力があった。それ以外の仮説的な論も。外国人に説明するのに役立ちそう。2015/08/16