|
 |
■
『赤い高粱』
莫言【著】、井口 晃【訳】
岩波書店(2003-12出版)
ISBN:9784006020798
〔中国〕
莫言は中国のマジック・リアリズムの旗手。土着的パワーと想像力のスケールの大きさ、奔放なイメージに関しては現代世界で最重量級。中国文学に対してだったら、やはりこういう作家にノーベル文学賞が行くべきではないかと思う。個人的には『花束を抱く女』や『酒国』が好きなのだが、残念ながらどちらも絶版。この『赤い高粱』では、中国の農村を舞台に、土と血と酒の強烈な香りに包まれた荒々しい物語が展開する。 |
|
 |
■
『砂時計』
ダニロ・キシュ【著】、奥 彩子【訳】
松籟社(2007-01-31出版)
ISBN:9784879842480
〔ユダヤ=セルビア〕
ダニロ・キシュは、ユダヤ系のセルビア語作家。すでに『若き日の哀しみ』『死者の百科事典』(どちらも山崎佳代子訳、東京創元社)の二冊が翻訳されているが、最近出た『砂時計』は、たぶんキシュの作家としての可能性をもっともよく示す作品だろう。アウシュヴィッツに消えた父の書いた手紙をもとに、当時父が考えたことを想像し、再構成したという複雑な仕掛けを通じて、失われた時間が甦る。難しい作品だが、見事な翻訳で読ませる。
|
|
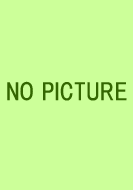 |
■
『森の中で』
ジョナス・メカス【著】、村田郁夫【訳】
書肆山田(1996-03出版)
ISBN:9784879953759
〔リトアニア=アメリカ〕
リトアニアからアメリカに亡命し、ニューヨークで活躍する実験映像作家メカスは、じつは母語のリトアニア語で作品を書く詩人でもあった(彼の名前はリトアニア語では、ヨーナス・ミャーカスと発音される)。深い森の中での自分の彷徨を描きだすこの長編詩は、難民としてアメリカに渡ってきたメカス個人の体験を投影したものだが、その背後にあるのは、故郷リトアニアの森であり、さらに第二次世界大戦によって荒廃したヨーロッパ文明そのものに他ならない。世界と向き合う孤独な放浪者の、繊細でいて強いまなざしに貫かれた佳品。
|
|
 |
■
『存在の耐えられない軽さ』
ミラン・クンデラ【著】、千野栄一【訳】
集英社(1998-11-25出版)
ISBN:9784087603514
〔チェコ=フランス〕
プラハの春を背景に、男女の愛を独自の官能的形而上学の視点から描いた、エロティックかつ思索的な小説。存在の「軽さ」「重さ」「キッチュ」といったキーワードについての哲学的考察が、政治的事件や恋愛と交錯する。作者クンデラはチェコからフランスに亡命、いまではフランス語で執筆するようになったが、作家としての力は圧倒的にチェコ語時代のほうが上だろう。この作品は『冗談』『可笑しい愛』と並ぶ、チェコ語で書かれた彼の最良の作品の一つ。
|
|
 |
■
『壁に描く』
マフムード・ダルウィーシュ【著】、四方田犬彦【訳】
書肆山田(2006-08-30出版)
ISBN:9784879956835
〔パレスチナ〕
アラブ世界を代表するパレスチナ詩人の作品集。評論家の四方田犬彦は自身、独自の構築力と明晰で力強い文体を持った詩の書き手でもあり、その能力が訳詩にも発揮され(主として英訳からの重訳のようではあるが)、パレスチナをめぐる複雑な歴史的事件に翻弄されながらも、祖国解放のために戦ってきた詩人の雄弁な声が響いてくる。詩は内面への耽溺ではなく、コミットメントなのだ。
|
|
 |
■
『遠い場所の記憶―自伝』
エドワード・W・サイード【著】、中野真紀子【訳】
みすず書房(2001-02-20出版)
ISBN:9784622032069
〔パレスチナ=アメリカ〕
エルサレムでパレスチナ人の両親のもとに生まれ、エジプトを経て、ニューヨークに至った文芸理論家サイードが前半生を振り返り、「失われてしまった人生の断片や人々のところに戻ろうとした試み」。サイードは言語的にも文化的にもきわめて複雑な環境の中に育ち、終生自分がいるべき場所にきちんと収まらずにさ迷い続けているという感覚に悩まされてきた。そういった人間の自我の芽生えと確立をたどった自伝の傑作。
|
|
 |
■
『それぞれの少女時代』
リュドミラ・ウリツカヤ【著】、沼野恭子【訳】
群像社(2006-07-29出版)
ISBN:9784903619002
〔ロシア〕
日本では『ソーネチカ』(新潮社)で知られるようになった現代ロシアの女性作家、ウリツカヤによる連作短編集。1950年代前半のソ連というスターリン独裁の厳しい時代を背景に、少女たちの幼い憧れや悩み、切ない愛や憎しみを、くっきりと描きわけ、時と場所の規定を越えて読者の心に迫るリアリティが感じられる。
|
|
 |
■
『テヘランでロリータを読む』
アーザル・ナフィーシー【著】、市川恵里【訳】
白水社(2006-09-20出版)
ISBN:9784560027547
〔イラン=アメリカ〕
イスラム革命後のイランで、大学を追われた英文学教師が、学生たちと「禁じられた本」を読んだ記録を綴ったもの。全体主義的な統制の下に置かれた国で、『ロリータ』のようなきわどい小説を読むことは、私たちに想像できないほど困難だったに違いない。そして彼女は、読解を通じて他者に対する想像力を鍛えることを教え、小説の自由が「あらゆる全体主義的な物の見方」に対抗するものだと主張する。小説を読むことの根本的な力に触れていて、感動的。ただし、民主主義を標榜する大国の、反全体主義キャンペーンに利用されないよう、ご用心。
|
|



