|
 |
■
『かばん』
セルゲイ・ドナートヴィチ・ドヴラートフ【著】、ペトロフ=守屋 愛【訳】
成文社(2000-12-25出版)
ISBN:9784915730276
〔ロシア=アメリカ〕
旧ソ連レニングラードで育ち、アメリカに亡命、ニューヨークで惜しくも若くして亡くなった、わが偏愛する作家、ドヴラートフの代表作。亡命の際に「かばん」に詰めて持ち出した品物の一つ一つの由来を説明する連作短編集になっている。いずれも繊細なユーモアとアイロニー、そして飄々たる感じがとても懐かしく、読んでいると笑いたくなったり、泣きたくなったりする。
|
|

 |
■
『ロリータ』
ウラジーミル・ナボコフ【著】、若島 正【訳】
<単行本>
新潮社(2005-11-30出版)
ISBN:9784105056056
<文庫>
新潮社(2006-11-01出版)
ISBN:9784102105023
〔ロシア=アメリカ〕
いわずと知れた英露バイリンガル作家にして言葉の魔術師、ナボコフが英語で書いた代表作。ナボコフの文章を読みぬいた若島正の新訳のおかげで、ロリータが現代的な少女として生き生きとよみがえった。「ロリコン」の元祖くらいにしかこの作品のことを知らない読者は、ともかくこの本を手にとって、ナボコフの言葉の技に感嘆してほしい。同じナボコフがロシア語で書いた長編の最高峰『賜物』も、ロシア語からいい新訳が早く出ないものか。
|
|
 |
■
『トランス=アトランティック』
ヴィトルド・ゴンブローヴィッチ【著】、西 成彦【訳】
国書刊行会(2004-09-30出版)
ISBN:9784336035943
〔ポーランド=アルゼンチン〕
20世紀ポーランドが生んだ鬼才ゴンブローヴィチが、アルゼンチンの亡命時代に書いた長編。ゴンブローヴィチの作品の中でも一番大胆な実験的文体で書かれており、ほとんど翻訳不可能と思われたが、原著者と同じくらいユニークな思想家である訳者がその文体に肉薄し、亡命と言語をめぐる恐怖と笑いのドラマが日本語で動き出す。 |
|
 |
■
『シカゴ育ち』
ステュアート・ダイベック【著】、柴田元幸【訳】
白水社(2003-07出版)
ISBN:9784560071434
〔ポーランド系アメリカ〕
「ウィンディ・シティ」(風の町)シカゴに、風に吹かれるようにしては集まり、また散って行く様々な移民たちの織りなす、多彩でちょっと物悲しい人生模様を浮かび上がらせる短編集。決して帰れない故郷オデッサの市街図を壁にはっている老ロシア人教師。世界中を放浪して歩いてきたポーランド人の「ジャ=ジャ」(おじいちゃん)。眠りながら笑い声をあげるギリシャ系の女の子……。翻訳の巨匠、柴田元幸の仕事は多すぎてとてもフォローしきれないが、アメリカでもさほど有名ではないこの作家を発見したことは、彼の大きな手柄の一つだと思う。
|
|
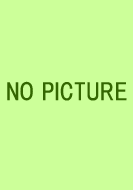 |
■
『救われた舌―ある青春の物語』
エリアス・カネッティ【著】、岩田行一【訳】
法政大学出版局(1981-10出版)
ISBN:9784588120466
〔東欧ユダヤ〕
エリアス・カネッティはユダヤ系の多言語性と越境性を一身に背負った作家である。セファルディ(スペイン系ユダヤ人)の血を引き、ブルガリアに生まれ、ウィーンに学び、ロンドンに移住してイギリス市民権を取りながら、ドイツ語で書き続け、晩年はチューリッヒで暮らした。ラディノ語、ブルガリア語、英独仏語に通じていた。『救われた舌』はこの稀有の「世界市民」がいかに形成されたか、その原点を探るかのように幼時から青年期までを回想したもの。「舌」は文字通り、危うく切り取られそうになった物理的な意味での器官であると同時に、コトバそのもののことでもある。
|
|
 |
■
『悪童日記』
アゴタ・クリストフ【著】、堀 茂樹【訳】
早川書房(2001-05-31出版)
ISBN:9784151200021
〔ハンガリー=スイス〕
アゴタ・クリストフはハンガリー人女性だが、1956年にハンガリー動乱を逃れ、乳飲み子を連れて亡命した。そして、スイスに住んで働きながらフランス語を習得し、この作品でデビューしてセンセーションを呼んだ。双子の兄弟「ぼくら」が、まるで作文の練習のようなたどたどしい文体で綴ったこの「日記」は、戦時下に疎開して、そこで悪に直面しながら非情に生き延びていく姿を浮き彫りにする。しかし、謎めいた部分が多く残され、それは続編の『ふたりの証拠』『第三の嘘』で解明されていく。亡命者が亡命後、執筆言語を切り替えて母語以外の外国語で作品を書く、というのは、じつは多くの場合、恵まれたインテリの場合だが(ナボコフ、クンデラなど)、クリストフはその対極のケースといえるだろう。
|
|
 |
■
『移民たち―四つの長い物語』
W・G・ゼーバルト【著】、鈴木仁子【訳】
白水社(2005-10-10出版)
ISBN:9784560027295
〔ドイツ=イギリス〕
ゼーバルトはドイツ生まれだが、20代でイギリスに渡り、そこで大学教師をしながら小説をドイツ語で書き続けた。2001年、57歳の若さで交通事故のせいで急逝、作家本来の可能性を出し尽くさずに亡くなってしまった感があるが、それでも残された作品を見ると、20世紀末にもっともよい小説を書いていた一人だということがわかる。長編『アウステルリッツ』でも、4人の登場人物の生を追った『移民たち』でも、写真や記事、メモといった小道具が多用され、フィクションとノンフィクションの間の境界も曖昧しながら、主人公たちは越境を続ける。知的に構築された文章は必ずしもとっつきやすいものではないが、鈴木仁子さんの訳文は見事で、きっと原文と同じくらいの水準なのだろうな、と思ってしまう。 |
|
 |
■
『容疑者の夜行列車』
多和田葉子【著】
青土社(2002-07-07出版)
ISBN:9784791759736
〔日本=ドイツ〕
多和田葉子はドイツに住み、日本語とドイツ語の両方で創作をするバイリンガル作家である。そして世界中を飛び回って朗読やパフォーマンスを行い、「エクソフォニー」(母語の外に出る旅)を精力的に実践してきた。長編『容疑者の夜行列車』の主人公「あなた」もまた、「永遠の乗車券」を持って「雲や水のように、土地から土地へと流れ」ていく。「みんな、ここにいながら、ここにいないまま、それぞれ、ばらばらに走っていくんです」。現代の人間のあり方、小説のあり方の本質をついた小さな傑作。
|
|



