|
 |
■
『国境の越え方 国民国家論序説』
西川長夫【著】
平凡社(2001-02-07出版)
ISBN:9784582763805
「起源の神話を打破しなければならない。『純粋な文化』は国民国家のイデオロギーが作りあげた幻想にすぎない。純粋な文化に対して雑種文化があるのではなく、文化とは本来、雑種的なものであろう」と、西川はいう。「国家=民族」幻想から逃れるためには、実際の国境を歩いて越える必要がある。国境地帯の「雑種」の文化の多様さや豊かさに触れることで、心の中に刷り込まれた民族神話や国民国家のイデオロギーの呪縛から自由になる契機を得る。 |
|
 |
■
『オムニフォン <世界の響き>の詩学』
管啓次郎【著】
岩波書店(2005-02-24出版)
ISBN:9784000223829
「世界の多様性は、世界のすべての言語を必要とする」。管啓次郎はカリブの思想家エドゥアール・グリッサンの詩学をそうパラフレーズし、〈オムニフォン〉を「あらゆる言語が響きわたる言語空間」と定義する。管は「ひとつの言語にはつねに他の複数の言語が滞在している」といい、「間に合わせの言語」としてのピジン言語の中に〈世界の響き〉をかいま見る。異質な言語どうしの接触から生まれる人間どうしの繋がりのはじまり。そこに現代文学の可能性を見る。 |
|
 |
■
『荒野のロマネスク』
今福竜太【著】
岩波書店(2001-08出版)
ISBN:9784006020361
チャトウィンが「砂漠」を志向するとすれば、今福龍太が志向するのは「荒野」だ。「荒野」とは、「ぼくたちのすむ都会のはずれに、それに接続するようにひろがっている荒れ果てた、しかし力強い意識の風景だ」と、
今福はいう。そうした混血の「発生」への兆しが感じられる「荒野」を記述しようとき、従来の科学的な言語ではない、新たな言語が必要とされた。それは「詩と直感とイマジネーション」にもとづく言語だった。チカーノ文化に興味ある者にとって、「バリオの詩学」や「国境文化の『放蕩息子たち』──
アメリコ・パレデス論」が刺激的だ。 |
|
 |
■
『鶴見俊輔集〈11〉 外からのまなざし』
鶴見俊輔【著】
筑摩書房(1991-09-15出版)
ISBN:9784480747112
本書の根幹をなすのは、「メキシコ・ノート」という副題のついた「グアダルーペの聖母」論だ。〈褐色の聖母〉について、この本から学ぶことはいまでも多い。ただ、それだけではなく、クエルナバカのカトリック教会の壁に描かれた日本の「二十六聖人殉教図」や、メキシコで演劇の教師をしていて帰国することのなかった佐野碩のこと、田中英光の『酔いどれ船』を論じた「朝鮮人の登場する小説」など、日本と日本人を見据えるオルタナティヴな視点がすばらしい。
|
|
 |
■
『「日本人」の境界 沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮 植民地支配から復帰運動まで』
小熊英二【著】
新曜社(1998-07-10出版)
ISBN:9784788506480
小熊はいう。「『日本人』とは、どこまでの範囲の人びとを指す言葉であったのか」「その『日本人』の境界は、どのような要因によって設定されてきたのか」と。近代において、その時々の政府の政策によって、沖縄をはじめとする周縁地城や、台湾・朝鮮の植民地の人びとは「日本人」扱いされたり、「外国人」扱いされたりしてきた。「日本人」の定義の曖昧さを膨大な歴史的文献を通して証明する労作。 |
|
 |
■
『幻の漂泊民・サンカ』
沖浦和光【著】
文藝春秋(2004-11-10出版)
ISBN:9784167679262
サンカは、どこからやってきたのか? 沖浦は、柳田國男による説(日本列島の先住民ともいうべき、先史時代の〈山人〉にまで遡る)や、喜田貞吉による説(中世あたりの「賎民系集団」であるという)を否定し、「近世後期起源説」をとなえ、サンカを半漂泊民ととらえる。時の権力者であれば、後世の学者に役に立つような史料を残しもしようが、そうでない周縁の人民はそうしたものを残す可能性は少ない。だから長い時間をかけて信念をもって日本社会の周縁文化を調査してきた著者によって、上記のような結論が導き出されていくプロセスは感動的ですらある。 |
|
 |
■
『モロッコ流謫』
四方田犬彦【著】
新潮社(2000-03-05出版)
ISBN:9784103671039
すでに『月島物語』(集英社)で試みた、個人的な視点に立つルポルタージュと文化史的研究の交じり合ったハイブリッドな文体を援用して、さらに大きな対象をとらえようとした力作。ヨーロッパから見て地中海の向う側の小国モロッコのいまと昔を語って、一括りには論じられない世界各地の植民地主義の問題を考えるヒントを提供する。文学や絵画や音楽や食など、モロッコに対する文化史的知識は、まるで無限の青を湛える砂漠の空のように豊かだ。 |
|
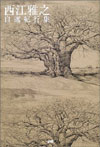 |
■
『西江雅之自選紀行集』
西江雅之【著】
JTBパブリッシング(2001-12-01出版)
ISBN:9784533040337
かつてアフリカのスワヒリ語の辞典を作ったハダシの文化人類学者・西江雅之のベストエッセイ集。「モロッコ、砂漠紀行」と題された文章の中で、著者は、サハラ砂漠の砂地に描かれた風紋を、首から上のない(そして足首から先もない)女体に喩えている。その女の体内に埋もれて死んでゆくというヴィジョンが強烈だ。西江雅之はどこかで「皮膚の外はみな異郷」という世界観を語っていたが、そうした世界観をハダシで歩く旅で得たに違いない。 |
|
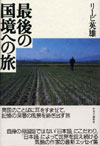 |
■
『最後の国境への旅』
リービ英雄【著】
中央公論新社(2000-08-10出版)
ISBN:9784120030390
著者はいう。「フランス・ワインはある種の『漢語』である。それに対して、カリフォルニアの、特にカベルネ・ソービニヨンは、『仮名混じり』の味がする。しぶみの中から、何とも言えない甘さが滲み、これを飲んでいる人に常に感覚的な驚きを覚えさせるのだ。……『原型』にこだわり、ヨーロッパの『権威』に弱い人には、その味が分からないだろう。しかし、そういう人には漢語から遊離してしまった日本語の『新しさ』にも気づくはずはない」と。日本語の使い手=日本人という、多くの日本人が信じて疑わない文化ナショナリズムを打ち消す〈日本語小説家〉のコトバに耳をすまそう。
|
|
 |
■
『徹夜の塊 亡命文学論』
沼野充義【著】
作品社(2002-02-22出版)
ISBN:9784878934476
日本文学を扱った『W文学の世紀へ』(五柳書院)でもそうだが、ロシア・東欧の文学を扱った本書は「異邦人のまなざし」に貫かれている。そうしたアウトサイダーのまなざしで見ると、世界が違ってみえてくる。現代ロシア文学を支えてきたのは、ロシア語で書く少数民族出身者であったりユダヤ人であったりするという発見。ロシアの国民的詩人プーシキンの祖先にアフリカの血がまじっているという事実。クンデラはマイナーなチェコ語で書いていたときの作品のほうがより普遍的な価値を持っていたという提言など、あっと驚く発見が満載。 |
|
 |
■
『日本語で生きるとは』
片岡義男【著】
筑摩書房(1999-12-16出版)
ISBN:9784480816160
片岡義男によれば、外に向けて経済的な成功をおさめるために、日本という国は、一個人の意見というものを抑圧・統制し、裏ルールの横行する世界を作ってきたという。だから、日本語の決まり文句を英語に平気で持ち込もうとする心情が抜けない。片岡による解決への提案は明るく楽天的だ。しがらみを捨てた個人の対話が可能な社会、論理的な日本語のやりとりが尊重される組織を作ればいい、失敗をしてもゼロからの出発を許すような社会システムを作ればいい、というのだ。 |
|
 |
■
『旅のエクリチュール』
石川美子【著】
白水社(2000-06-25出版)
ISBN:9784560046807
石川美子によれば、一般読者はノンフィクション形式の紀行文や旅行記に著者の作為(フィクション)を読みとり、逆に説話的な旅物語に同時代への批評的な言及を読みとりがちだという。石川は13世紀のマルコ・ポーロによる実録『東方見聞録』と、17
世紀から18世紀にかけて流行した空想旅行物語(『ガリヴァー旅行記』など)を例に引いて、「旅のエクリチュール」について、そうした面白いパラドックスを指摘する。 |
|
 |
■
『トラウマの声を聞く 共同体の記憶と歴史の未来』
下河辺美知子【著】
みすず書房(2006-06-25出版)
ISBN:9784622072188
フロイトは、『モーセと一神教』で、通常個人に対して使われる「外傷性神経症」をホロコーストにあったユダヤ民族という集団に当てはめ、一大仮説を打ち立てた。下河辺は、その経緯を丁寧に追いながら、21
世紀のPTSD について論及する。それは、「核」という脅威にほかならない。「テロの威嚇」という言葉だけが一人歩きして、PTSD
の〈麻痺〉に現代社会が陥っており、人類は最大のジェノサイドの危機にあると提言する(「集団のトラウマという発見」)。 |
|
 |
■
『棗椰子の木陰で―第三世界フェミニズムと文学の力』
岡真理【著】
青土社(2006-07-07出版)
ISBN:9784791762811
著者は気鋭の現代アラブ文学者。現代アラブ文学とは何だろう、と問いを立てる。「第三世界」のアイデンティティを問うそうした姿勢は、さらなる根源的な問いに向かう。「第一世界」に入れられている日本人の「わたし」は、果たしてイスラーム世界に対する「オリエンタリズム」の眼差しを避けられるのか、と。通常イスラーム社会の家父長制の犠牲者として見られがちの、「特権」ない女性にもしたたかな別の語りがあるということをスリリングに語る良書だ。 |
|
 |
■
『カフカ寓話集』所収
「ある学会報告」
フランツ・カフカ【著】、池内紀【編訳】
岩波書店(2003-02-17出版)
ISBN:9784003243848
アフリカで捕えられたサル(私)が、「文明」の地で唾の吐き方や罵倒の仕方を覚えたりして、いかに人間として「進化」を遂げたかを、ヨーロッパ的「知」の結集の場ともいうべき学会で語るという形式を取る。ココ・フスコはこの物語を、コロンブスの新大陸「発見」以降、ヨーロッパで行なわれてきた「人類展覧会」の隠喩としても読めると指摘。たとえ学問的な興味からであっても、「人類展覧会」の裏には、オリエントやアフリカに対するヨーロッパの優越思想が隠されている。カフカは、そうしたヨーロッパの「他者」への無意識の優越感と、その裏返しとしての恐怖心を突いているのだ。 |
|
 |
■
『ベンドシニスター』
ウラジーミル・ナボコフ【著】、加藤光也【訳】
みすず書房(2001-02-22出版)
ISBN:9784622048039
ナボコフ自身は「序文」で、この小説が「地口」からなるとし、それが「文体的歪曲」であるという。しかし、この小説の主題の一つが警察国家の「グロテスクな非人間性」であってみれば、抵抗文学のまっすぐな文体よりも、まるでファンハウスの歪んだ鏡のようにそれ自体が人間や組織の狂気を映しだす、カフカにも似た「文体的歪曲」こそが相応しいのではないか。さらに、ナボコフはこの小説を単純な「寓意小説」として読まないよう、読者にあらかじめ釘をさしている。が、この小説を活気づけているのが毒を効かせた体制への容赦ない諷刺精神ブラックユーモアであることも事実なのだ。 |
|
 |
■
『トランス=アトランティック』
ヴィトルド・ゴンブローヴィッチ【著】、西成彦【訳】
国書刊行会(2004-09-30出版)
ISBN:9784336035943
ゴンブローヴィッチは、〈回転〉のモチーフをふんだんに用いて読者に眩暈めまいを起こさせながら、アルゼンチンに住むポルトガル人とトルコ人の「混血」の大富豪ゴンサーロに託して、ヨーロッパにおける大戦と自身の亡命生活の不条理を笑いのめす。新大陸アルゼンチンにおけるポーランド人共同体において〈祖国〉の文化伝統や権威といったお題目を唱える退屈な知識人連中に対して、ブラックな風刺をまぶしたラディカルな批判を浴びせる。 |
|
 |
■
『移民たち 四つの長い物語』
W・G・ゼーバルト【著】、鈴木仁子【訳】
白水社(2005-10-10出版)
ISBN:9784560027295
ゼーバルトと死者たちとは、「絶望」で繋がっている。死者たちがゼーバルトに憑依して、作品の中では「事実」と「虚構」の境界がぼやける。ゼーバルトはそういう意味での霊能者・詩人であり、いわば声なき死者のための代書屋だ。ノンフィクションのトラヴェル・ライティングだと思って読んでいると、あまりにできすぎたフィクションのような「
偶然」に驚かされる。読者はその「はざま」の世界にとり憑かれる。 |
|
 |
■
『雪』
オルハン・パムク【著】、和久井路子【訳】
藤原書店(2006-03出版)
ISBN:9784894345041
トルコの現代小説家オルハン・パムクは、9・11以降に急激に欧米で読まれだした作家。魅力的なイスラム過激派のリーダーも出てくるが、特定のイデオロギーを代弁する小説ではない。むしろ、世界の情勢と切り離されて生活しているように見えても、現代人はそれとは無関係には生きられないといったことを伝える「政治小説」だ。しかも、エーコやマルケス、オースターなどを知った小うるさい読者の読解にも耐える語りのワザを備えたポストモダン小説。日本語の訳がひどいのが残念だが……。 |
|
 |
■
『アルゲダス短編集』
ホセ・マリア・アルゲダス【著】、杉山晃【訳】
彩流社(2003-06-30出版)
ISBN:9784882028239
ペルーには山岳文化と海岸文化の違いがあるらしい。首都リマに代表される海岸地方が欧米風の近代主義をとり入れ、合理的な思考を尊ぶのに対し、アンデスの山地は、いまなおインディオの神話の中に生き、山や木の精霊を語り、ときに濁流となって暴れ狂う川に畏怖の念を抱く。20世紀のペルーを代表する小説家であり、民俗学者でもあったアルゲダスが描くのは、そうした二つの文化のぶつかり合いだ。短篇のほとんどの舞台が山岳でもなく海岸でもない、その中間の麓の草原地帯(パンパ)であるのも、そうした理由だろう。 |
|
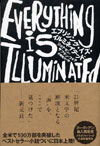 |
■
『エブリシング・イズ・イルミネイテッド』
ジョナサン・サフラン・フォア【著】、近藤隆文【訳】
ソニー・マガジンズ(2004-12-10出版)
ISBN:9784789724135
アメリカ文学の新星によるデビュー作。歴史的に隣接する大国に翻弄されてきた小国ウクライナの、ポーランドとの国境地帯が舞台。東欧出身の米国ユダヤ系移民の〈自己探求〉の旅+〈東ヨーロッパの近代史の問い直し〉というテーマが、I・B・シンガー顔負けの、イディッシュの口承文芸の伝統に裏打ちされた法螺話や、エロティック・コミックの下ネタ満載の語りで読み応えたっぷりに展開。でも、テーマはぐっと重たいホロコーストだ。ホロコーストを口実にして、ユダヤ民族中心主義に陥らない点が美点。 |
|
 |
■
『小さな場所』
ジャメイカ・キンケイド【著】、旦敬介【訳】
平凡社(1997-04-16出版)
ISBN:9784582302226
イギリスの植民地だったカリブ海のアンティガ出身で、現在、米国在住のキンケイド。いわばポストコロニアルな作家のひとり。舞台は、いつも南のカリブ海。フランツ・ファノンではないが、イギリスの植民地であることをやめても、住民の心に〈植民地根性〉が刷り込まれてしまっていることを二人称の語りでしめす。短篇集『川底に』(管啓次郎訳、平凡社)
を併せて読むと、カリブの小島の「周縁」の人びとの生がこのグローバリゼーションの時代を先鋭に反映していることが分かるだろう。 |
|
 |
■
『見えない人間』<1巻><2巻>
ラルフ・エリスン【著】、松本昇【訳】
南雲堂フェニックス(2004-10-12出版(1巻)、2004-10-12出版(2巻))
ISBN:9784888963350(1巻)、9784888963367(2巻)
半世紀以上も前に刊行されながら、ますます威光を放つアメリカ文学の傑作。というより、このグローバルな時代における世界文学の傑作だ。のけ者はひとり黒人のみならず、移民もまた「見えない人間」として社会から押しのけられる。ポスト資本主義の格差社会によって、移民女性、ホモセクシュアル、ホームレスなど、「見えない人間」として周縁に追いやられる人の数は増大。社会を下層から見つめる語り手のアイロニカルでユーモアのある語りがすばらしい。 |
|
 |
■
『ソングライン』
ブルース・チャトウィン【著】、芹沢真理子【訳】
めるくまーる(1994-07-20出版)
ISBN:9784839700782
[ 品切・入手不可 ]
ブルース・チャトウィンは、〈砂漠〉の放浪者(ノマド)として、中央オーストラリアの乾燥地帯をほっつき歩いた。放浪癖に偏執的に囚われ、自分が、そして人類が放浪するのはなぜか? と問い、〈人類のふるさとは砂漠にあり〉という結論を引きだしてくる。一見なんの変哲もない土地に見えるのに、チャトウィンの語るオーストラリアの砂漠は、なぜかアボリジニの詩がいっぱい詰まった心豊かな風景と化す。 |
|
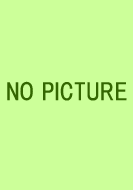 |
■
『越境』
コーマック・マッカーシー【著】、黒原敏行【訳】
早川書房(1995-10-31出版)
ISBN:9784152079602
[ 品切・入手不可 ]
『神の子』や『サトリー』など、おもにテネシーを舞台にした小説で高い評価を得ていたマッカーシーだが、『すべての美しい馬』に始まる〈国境三部作〉によって商業的にも大ブレークした。マット・ディロン主演の映画になったこの作品よりも、実は二番目の『越クロッシング境』のほうが質量ともに優れている。 |
|
 |
■
『ザ・ライフルズ』
ウィリアム・T・ヴォルマン【著】、栩木玲子【訳】
国書刊行会(2001-02出版)
ISBN:9784336039613
本書をふくむ全7巻のシリーズは、著者自身によって「7つの夢」と名づけられ、北米におけるヨーロッパ文化と原住民文化との衝突と融和を扱う。本書では、ヨーロッパ勢力(たとえば、19世紀イギリス帝国)の北極圏探検の背後にあった政治的イデオロギーや人間的な軋轢などを再発見する一方で、迫害の憂き目にあってきた原住民(強制的に移住させられたカナダのイヌイット)の現在を、先住民側の視点から語り直す。 |
|
 |
■
『昏き目の暗殺者』
マーガレット・アトウッド【著】、鴻巣友季子【訳】
早川書房(2002-11-30出版)
ISBN:9784152083876
4種類の語りを混ぜこぜにした複雑な構成をとる。老女(83歳)アイリスの語るチェイス家一代記。地方新聞の記事、ゴシップ誌の切り抜き。アイリスの妹ローラの作とされる不倫小説『昏き目の暗殺者』。その不倫小説の主人公の男が語る猟奇的SFファンタジー。作者アトウッドの頭の中には、後に“戦争の世紀”と呼ばれる20世紀のカナダ史の暗い側面を、ブルジョワ娘とプロレタリアート青年との不倫物語を通して語るという壮大な企図があったのではないか。 |
|
 |
■
『ケリー・ギャングの真実の歴史』
ピーター・ケアリー【著】、宮木陽子【訳】
早川書房(2003-10-31出版)
ISBN:9784152085238
すでに『イリワッカー』(1985年)や『オスカーとルシンダ』(1988年)など、スケールの大きい〈歴史改変小説〉によって、英語圏のガルシア・マルケスとも目されるケアリーだが、本作はかれの作品のなかでも最高傑作ともいいうるものではないだろうか。流刑囚移民の末裔の視点からオーストラリアの歴史を語りなおしたポストコロニアル小説としても、社会の最下層の「悪党」を主人公にした冒険小説としても、未開の奥地を描いたネイチャー・ライティングとしても読める。 |
|
 |
■
『グールド魚類画帖 十二の魚をめぐる小説』
リチャード・フラナガン【著】、渡辺佐智江【訳】
白水社(2005-07-10出版)
ISBN:9784560027233
『ケリー・ギャングの真実の歴史』と同様、植民地時代のオーストラリア史を声なき囚人の側から書き換える「悪漢小説」であり、かつ産業資本主義文明を批評する「ファンダジー小説」であり、博物学的な構成を有する奇書だ。アザラシ猟師たちによるアボリジニの集団虐殺をはじめ、数々の惨劇を散りばめるだけでなく、新大陸の原野にヨーロッパを再現すという無謀な、しかし現在までつづく文明人たちの狂気の夢も描く。 |
|
 |
■
『ガラテイア2.2』
リチャード・パワーズ【著】、若島正【訳】
みすず書房(2001-12-20出版)
ISBN:9784622048183
ギリシア神話によれば、ガラテイアというのは、キプロス王ピグマリオンが創った女性の彫刻の名前だが、皮肉にも、女嫌いで有名なピグマリオンは自分の創った彫刻に魅せられてしまったという。この小説でも、十年も付き合った恋人を失ったばかりの、失意の小説家の「僕」がフィリップ・レンツという名の科学者の手を借りて、コンピュータH機号(別名、ヘレン)
に「ことば」を教えていくうちに、そのマシンに恋してしまい、そして裏切られる。人間と機械の境域を扱う。 |
|
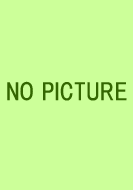 |
■
『ラフカディオ・ハーン著作集 第14巻』所収
「ゴンボ・ゼーブス」
ラフカディオ・ハーン【著】
恒文社(1983-11出版)
ISBN:9784770405388
ハーンは日本に来る前にカリブ海のフランス領マルティニークに滞在し、小説『ユーマ』を書いた。その前に暮らしたのが米国南部のニューオーリンズ。この街は、そうした腰の据わらない旅人に格好のネタ(幽霊=人間の心理の闇)を提供した。一方、そこはカリブ海のクレオール語の宝庫でもあり、ハーンの興味は、このクレオール語の諺小辞典に結実した。 |
|
 |
■
『フランシスコ・X』
島田雅彦【著】
講談社(2002-04-26出版)
ISBN:9784062112871
主人公は、日本での布教に失敗したザビエル。島田の描くザビエルは、遠藤周作のイエスとちがい、まず肉体的に逞しい。実はバスク地方(ナヴァラ王国)出身者だったのだ。島田雅彦は、さまざまな宗教的な、社会的な、文化的なシンクレティズム(混交)がこの世界の現実であることをしめそうとしたのかもしれない。島田のザビエルは学者を目指しながら宣教師になり、アジアに派遣されてからは、次第に「純血」のカトリックから変身をとげてゆくのだから。 |
|
 |
■
『アメリカ 非道の大陸』
多和田葉子【著】
青土社(2006-11-15出版)
ISBN:9784791763047
この世にトラヴェル・ノヴェルは数多いが、ただ風景の珍しさを綴るだけでは面白くない。本書は北米の旅を二人称で語る。「あなた」は自動車の免許証がない。だから、運転できる現地人に頼ることになる。その人とつながりができ、物語が語られはじめる。これまでとは別の人間になりかわる場としての「アメリカ」。新しい人たちの力によって「アメリカ」自体もなりかわる。そんな生成する場の内側を覗く衝撃に満ちた小説だ。 |
|
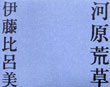 |
■
『河原荒草』
伊藤比呂美【著】
思潮社(2005-10-31出版)
ISBN:9784783721017
伊藤比呂美の久しぶりの詩集。父の死をはじめ、個人的な出来事がうっとうしいほどの荒草の繁る「河原」で起こる。河の中でも土手でもない、その中間としての「川原」で。「河原には死骸がある/いくらでもある/どんな生き物も殺して死骸にし/どんな死骸をもよみがえらせる……」。死者を送り、死者を呼びよせ、生きる意味を確かめる。そんな生と死の境域を、伊藤比呂美の「河原」は表わす。 |
|
 |
■
『僕はジャクソン・ポロックじゃない。』
ジョン・ハスケル【著】、越川芳明【訳】
白水社(2005-08-10出版)
ISBN:9784560027271 |
|
 |
■
『真夜中に海がやってきた』
スティーヴ・エリクソン【著】、越川芳明【編】
筑摩書房(2001-04-20出版)
ISBN:9784480831880 |
|
 |
■
『彷徨う日々』
スティーヴ・エリクソン【著】、越川芳明【訳】
筑摩書房(1997-04-20出版)
ISBN:9784480831736 |
|
 |
■
『翻訳家の仕事』
岩波書店編集部【編】
岩波書店(2006-12-20出版)
ISBN:9784004310570 |
|
 |
■
『スティーヴ・エリクソン(現代作家ガイド2)』
越川芳明【編】
彩流社(1996-11-25出版)
ISBN:9784882024026 |
|
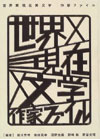 |
■
『世界×現在×文学―作家ファイル』
越川芳明、柴田元幸、沼野充義、野崎歓、野谷文昭【編】
国書刊行会(1996-10-24出版)
ISBN:9784336038821 |
|



