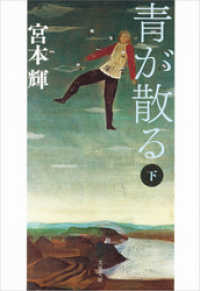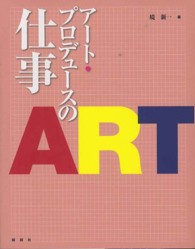内容説明
横溝、鮎川、清張、綾辻、有栖川…彼らはクイーンをどう受容し、いかに発展させたのか。本格ミステリに真っ正面から挑んだ渾身の評論。
目次
第1章 横溝正史―必然という呪縛
第2章 鮎川哲也―証拠という問題
第3章 松本清張―犯人という主体
第4章 笠井潔―社会という世界
第5章 綾辻行人―叙述という公正
第6章 法月綸太郎―創作という苦悩
第7章 北村薫―人間という限界
第8章 有栖川有栖―推理という光輝
第9章 麻耶雄嵩―探偵という犯人
第10章 その他の作家―女王という標石
著者等紹介
飯城勇三[イイキユウサン]
1959年宮城県生まれ。東京理科大学卒。エラリー・クイーン研究家にしてエラリー・クイーン・ファンクラブ会長。評論『エラリー・クイーン論』(論創社)で「本格ミステリ大賞・評論部門」を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
林 一歩
19
あくまで私的な好みの問題にはなりますが、ヴァン・ダイン<クイーン<クリスティー<カー という順列な人なので、クイーンに影響を受けた国内ミステリー作家に諸作品に関する考察ってのは退屈極まりない。好みの問題なので、否定はしませんけど。着眼点は良いと思うんですよ。同様に他の作家さんたちについても論じてくれるなら言うことは無いんだけど…。要は、私は余りクイーン作品を高く評価してない人間なので、その一点突破はしんどいなと。2014/04/13
kate
17
エラリー・クイーンを切り口に日本の本格作家を考察し評論していくもので好きな作家も多く自分でも色々考えてたりした人達ばかりなので楽しめました。クイーン論のほうも読んでみたいですね。2014/02/02
飛鳥栄司@がんサバイバー
7
お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。おかわりは、あとがきにも書かれていましたが、J.D.カーの騎士たちを希望です。 乱暴な言い方かもしれないけれど、本格ミステリが行き着く(帰るべきところ)は、エラリー・クイーンと言うことなのだという著者の思いが強く伝わってくる。取り上げられている日本を代表する本格ミステリ作家の根底にあるのは、クイーンであるという論理にも説得力があり、とても楽しく読めた。この本を酒の肴にして、ちょっとしたミステリ読みの仲間と語りあったら酒を飲むのもそこそこに朝まで語るんだよ、きっと。2013/10/26
kokada_jnet
6
法月綸太郎を論じた章で描かれる、近年あきらかになったという、ダネイとリーの独特の「合作方法」が興味深かった。そうだったのか!という感じ。岡嶋二人と同じ役割分担だけれど、ミステリの合作では、普遍的な方法なのかな。(考えてみたら、漫画の原作・作画の分担と同じなのだった)2013/11/02
hanchyan@そうそう そういう感じ
6
ものすごく面白かった。手近に置いて今後なんども読み返すと思う。「・格章の最初に、その章で真相等に言及している作品名を揚げている」にビビりつつ、ままよ!と読みました。<犯人あて>と<トリックあて>、“犯人側の都合”と“作者側の都合”、探偵が“ヒーロー”か否か、etc…。構造主義的に解題されてゆく名作の数々・・・!! 自分ダメじゃん!!フフン♪とかいってる暇あったら巻末の引用・参考資料一覧参考にしてもっと励め!! 著者が構想中の、カーとチェスタトンを切り口にした本もぜひ読みたいので、この本を支持します。2013/10/22