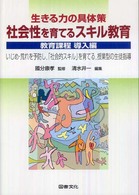目次
第1章 アドラー心理学の考え方(アドラー心理学の五つのポイントで教育が変わる!;賞罰に代わるアドラー心理学;授業に生かすアドラー心理学;学級経営とアドラー心理学)
第2章 子どもの不適切な行動の四つの目標(注目・関心を引く―適切な行動、あたりまえの行動を認める;権力争いをする―対等な「横の関係」で話をする;復讐する―傷つけ合う関係を脱する;無気力・無能力を誇示する―学級のあり方を見直す)
第3章 勇気づけ(勇気くじきの授業から勇気づけの授業へ―私の失敗「勇気くじき」とは;いまできていることに注目して勇気づける;挫折からアドラーへ―使える心理学)
第4章 共同体感覚(学級づくりに生かす共同体感覚;アドラー心理学のエッセンスたっぷり!「クラス会議」を始めよう!;共同体感覚を育む教師同士の関係づくり)
第5章 こんなときどうする(保護者からのクレーム;体罰をしそうになったとき;いじめに向き合う勇気づけの学級づくり)
著者等紹介
会沢信彦[アイザワノブヒコ]
文教大学教育学部教授。1965年、茨城県生まれ。筑波大学卒業、同大学院修士課程修了。立正大学大学院博士課程満期退学。函館大学専任講師を経て現職
岩井俊憲[イワイトシノリ]
有限会社ヒューマン・ギルド代表取締役。1947年、栃木県生まれ。早稲田大学卒業。外資系企業の管理者等を経て、1985年、有限会社ヒューマン・ギルドを設立。1986年、アドラー心理学指導者資格を取得。青森公立大学、函館大学非常勤講師。上級教育カウンセラー。ヒューマン・ギルドでアドラー心理学に基づくカウンセリングや公開講座、カウンセラー養成を行うほか、企業・教育委員会・学校から招かれ、カウンセリング・マインド研修、勇気づけ研修や講演を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Gatsby
すみけん
るい
えぬ
Taka