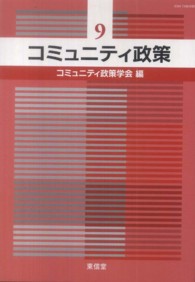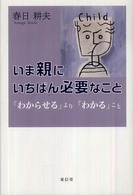内容説明
前著第1部で見た大学教員・学生間だけに限らず、すべての養育・教育場面で、これまで自明とされてきた関係の非対称性が力を失い、かわって技術的合理性の支配が露わになってきた。この危機のさなかで、新たな循環的・相互生成的な関係の成立可能性を追究する本書は、臨床的人間形成論に至るまでの京都学派以来の学問的系譜を精細に提示するとともに、没人間的な技術的合理性を超える根源的能動性、すなわち「パトス」としての人間の復権をめざす、渾身の力作である。
目次
序論 大学教育の臨床的研究から臨床的人間形成論の構築へ
第1章 臨床的人間形成論の系譜(臨床的人間形成論へ;京都学派と京都学派教育学;森昭の教育人間学から臨床的人間形成論へ)
第2章 人間形成論(教育人間学から人間形成論へ;人間形成論の構造(1)―発達、教育、教育目的、教育可能性の再考
人間形成論の構造(2)―相互性の人間形成論とライフサイクルの人間形成論)
第3章 臨床的人間形成論(絶句と臨床性;大学教育の臨床的研究;臨床的人間形成論の方法と構造)
第4章 臨床的人間形成論の展開(教育的公共性の臨床的人間形成論へ;世代継承性の臨床的人間形成論へ)
著者等紹介
田中毎実[タナカツネミ]
1947年、鳥取県生まれ。大阪大学大学院文学研究科単位取得退学。大阪大学助手(人間科学部)、愛媛大学助教授(教育学部)、同教授(同学部)、さらに京都大学教授(高等教育研究開発推進センター)、同センター・センター長を経て、武庫川女子大学文学部教授。京都大学博士(教育学)。教育哲学・大学教育学専攻。教育学の臨床的人間形成論への展開を企図している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。