|
|
  |
|
 |
 |
恩田 陸 [おんだ・りく] 92年、日本ファンタジーノベル大賞の最終候補作となった『六番目の小夜子』(新潮社)でデビュー。 ホラー、SF、ミステリなど、既存の枠にとらわれない、独自の作品世界で沢山のファンを持つ。 著書に、『球形の季節』(新潮社)『三月は深き紅の淵を』(講談社)『光の帝国 常野物語』(集英社)『図書室の海』(新潮社)『ライオンハート』(新潮社)『禁じられた楽園』(徳間書店)『Q & A』(幻冬舎)などがある。 |
| 撮影:中島 博美 |
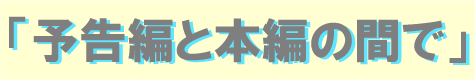 |
|
思えば、予告編が好きだった。 思えば、カタログが好きだった。 思えば、印刷物が好きだった。 企業のPR誌なんかもせっせと溜め込んでいた。印象に残っているのは、長崎屋の広報誌で、かなりミニコミっぽい「ひとりとふたり」という小さな雑誌があり、そこで初めて丸文字の元祖、ナール体に遭遇して衝撃を受けたことである。私は字を書くスピードが速いので、さんざん真似しようとしたがとうとうあの字をマスターできなかった。 |
そんなわけで、私はノートが大好きだった。ノートをやぶって真ん中で閉じ、雑誌らしきものを作るのが好きだったのである。罫のないノートを見つけた時には物凄く嬉しかった。だって、漫画の本も、小説本も、世の中の印刷された本には罫なんか入っていないからだ。そのノートを何冊も買ってもらい、漫画を描いたり、お話を書いたり、これから書く漫画の予告編を描いたりしていた。『大脱走』を観れば穴を掘って逃げる話を書き、『オヨヨ島の冒険』を読めば「あたしは」という一人称でお話を書いた。 けれど、当時の私は、一度もお話を最後まで書くことができなかった。いつもイメージばかりが肥大して、ちっとも書けないことに嫌気がさし、ほんの数ページでやめてしまってばかりいた。ひたすら予告編ばかり書いているうちに、大人になってしまったのだ。 そして、ようやく私は本編を書くようになった。やっと、おしまいのページまでお話を書けるようになったのである。しかし、子供の頃を振り返る時、決まって吉原幸子の詩の一節──「書いてしまへば書けないことが 書かないうちなら 書かれようとしてゐるのだ」という言葉をしみじみと噛み締める。 それはまだ──恐らくは最後まで──きっと分からないに違いないのである。 |
| NEXT>> |
Copyright by KINOKUNIYA COMPANY LTD.