

|
|
  |
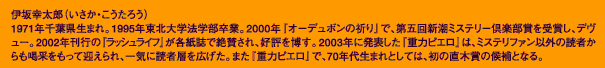 |
||||||
|
|
|
|
店のドアが開いた、と思ったら、」ずかずかと彼女が店内に入ってきた。僕の向かいの席に座ったとたんに、挨拶もなく、すごい剣幕ではなしはじめる。 |
「ひどい言葉には思えないけどな」 「買った本は全部読んでるみたいで、最近はやたら、詳しくなっちゃてるわけ。 『三島由紀夫に爽快な犯罪小説を書いてほしかったですよね』とか、『中上健次の短編“隆男と美津子”はミステリですね』とか、うるさいったらないわけ。しまいには、『この文庫本の隣にこの単行本を置いたら売れますよ』とか、『この本とこのノンフィクションは客層が一緒ですよ』とか、『こういうポップを掲げたら、客は手にとりますよ』とか言ってさ」 僕は、フォークを突き出したまま、「へえ」とか「ふうん」の中間のような声を発する。 「しかもさ」彼女はむくれた顔で、「言うとおりにやってみると、これが売れちゃうわけ。本当に、お客さんが本を手に取っていくんだよね。頭きちゃうでしょ」 「あのさ」剣幕に圧されながら、言う。 「何?」彼女は鼻息が荒い。 「その彼はさ」僕は遠慮しながらも、つづけた。「もはや、ストーカーとか、おとくいさんとか、そういうものではなくてさ」 「何よ」 「書店の救世主と呼びべきじゃないのかな」 「何それ、他人事みたいな言い方じゃない。わたしがつけまわされてるんだよ」 「他人事も何も、僕たちは他人じゃないか」 「そういう言い方ってひどくない?」 「それ以上、近づいたら刺すからね」僕は、二年前から僕を付け回すストーカーの女性、つまり目の前の女性に、フォークを向ける。人のふり見て我がふり直せって。 |
Copyright by Kinokuniya company ltd.