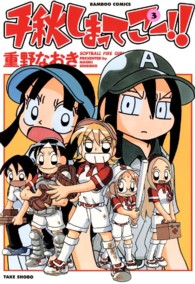内容説明
日本近代詩から萩原朔太郎へ、戦後詩の鮎川信夫や田村隆一、68年の天澤退二郎や吉増剛造、寺山修司、そして現在へと至る詩人たちが、詩史論に収まりきらない「文学」や「批評」の問題として描かれる。
目次
第1部 詩的モダニティの系譜(詩的モダニティの系譜―萩原朔太郎の位置)
第2部 “ポ”エティックの舞台(「市民」と「詩人」―鮎川信夫論;反=隠喩としての詩―北村太郎論;詩的モノローグの彼岸―田村隆一論;「おとづれ人」の書法―黒田喜夫論;散文=詩という逆説―岩田宏論 ほか)
第3部 日本近代文学の始まりと68年(ハムレット/ドン・キホーテ/レーニン―近代初頭における詩・小説・演劇;「呪われた詩人」と、その後―一九六八年の詩人たち)
著者等紹介
〓秀実[スガヒデミ]
1949年新潟県生まれ。「日本読書新聞」編集長、日本ジャーナリズム専門学校講師などを経て、近畿大学国際人文科学研究所教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
原玉幸子
15
私は「俳句や短歌には形式があるものの、詩はシニフィエを直截的な言語羅列で表現する様式(表現手法は抽象画と同質では!)」と考えていて、その仕組みに触れたくて選びました。『革命的な、あまりに革命的な』での左翼っぽい舌鋒の著者に、まぁ憧れに似た期待があったのですが、仕組み解説よりも詩を通じた社会評論なので、一言で言えば読者私の勉強不足。「詩を創作出来ない人間は、詩を評論するに適わぬ」に同意する以上は、もっと詩作を読み込まなければ……あぁ、選んで読むこと自体が格好悪かった。反省の再読候補本。(◎2021年・秋)2021/10/07
しゅん
10
詩を否定すべき抒情として傍に追いやりながら、「詩的」という言葉に頼りながら続いてきた日本近代文学。その矛盾の正体を朔太郎を中心に置いて捉える「詩的モダニティの系譜」が一番面白い。「芸術/実行」の対立が(強く政治性を帯びた)言文一致運動を駆動し、「実行」の詩として「口語自由詩」が登場する。否定/肯定、犯人/探偵、故郷嫌悪/故郷が一致する朔太郎の「故郷喪失における郷愁」は、芸術/実行ジレンマを解消する詩として誰も超えられない場に立つ。絓は、その全体主義的限界を越えるために、「言文一致」の「文」を問題化する。2021/08/14
no5uke
5
なかなか面白かった。 詩人の知識はそこまでないが、なかなか楽しめた。 60年代以降はかなり難解に感じる。2025/11/21
Gakio
2
その多くは「現代詩手帖」に1989年に連載された詩人論。入沢康夫の「詩は表現ではない」というテーゼが力強く、だからこそ私にとって現代詩は読む必要がないだろうと改めて思えた。それとかつてからある吉増剛造への生理的嫌悪感が増した。 総じて詩人のカタログだが、読了して一番読みたくなったのは、デリダの『哲学の余白』だ。2024/07/15
トックン
2
「詩的モダニティ」とは明治後期の口語自由詩運動を経てファシズムに収斂される昭和初期の大衆社会を経過することで醸成されてきた雰囲気。そして、これを小林・保田が<根拠を喪失した故郷=大衆>というテーマで「無気力化(アウフヘーベン)」した。「言」(詩=ポエジー)でなく「文」(エクリチュール)による戦後詩の分析で如何に我々が近代的装置に囚われているかを明らかにするのが主眼。特に「荒地」批判。鮎川的暗喩(表象=代理)&表出=疎外(吉本)というパラダイムを抜け出そうという試み。2017/04/22