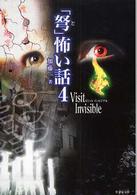- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
紙の前は何で拭いていたのか!?葉っぱ、藻、とうもろこし皮、木ベラ竹ベラ、藁、それから縄も?日本各地を訪ね歩いて聞き集めた便所にまつわる民族誌。
目次
1 葉(しーのぎっぱ;もぐ;かくま;柿;とうもろこし皮;藁;えびくさ;おさぐさ;がざ;蕗;葛;朴・栃・科;ひとつば;楢;ユーナ;縄)
2 ちゅうぎ(かぎん;うるし;竹;虎杖;竹似草;麻がら;茅・楮・桑)
3 便所(カワヤから溜へ;二本ばし;乾式便所;フール;下肥;直振り)
4 民俗(糞生ーれた;雪隠まいり;くそくらえ;汚物の呪力;夜糞どの;黙ったづんぎ転ばがた;くそ)
著者等紹介
斎藤たま[サイトウタマ]
1936年、山形県東村山郡山辺町に生れる。高校卒業後、東京の本屋で働く。1972年、埼玉県秩父市に移り住む
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こぽぞう☆
12
図書館本。前半3/4はひたすら、トイレで紙使うようになる前は何で拭いた(ぬぐった)か?である。正直「もうどうでもいーよ」となったが、読み通す。葉っぱが多いが、木ベラ的なものも多かったらしい。最後の方に、いかに「下肥」が貴重だったかも書いてあった。町育ちの私の実母が、父の実家でオムツを川で洗って叱られたが理由が今でもわからない、と言っているが、当時汲み取りだったトイレにすすぎ水まで入れるのが正確だったのだろうと、思い至った。父の実家は農家だったから。2018/09/19
takao
1
ふむ2024/10/17
k.shirokuma
0
下水があり、清潔な暮らしが当たり前の生活を送っているが、ほんの4、50年前までは、ボッチャンに、ちり紙で用を足していた。今から考えれば、不潔かもしれない。でも家族で、落とし紙のために、葉っぱを集める様子を、思い浮かべると、ほんのり暖かい気持ちになる。とは言っても、決して戻りたいとは思わない。2013/12/03
tengusa48
0
うんこをした後、何で拭く? 現代日本でそんな質問をしたら「何言ってんだコイツ」って目で見られます。そんなのトイレットペーパーに決まってますからね。でもそれが一般化する以前、日本人は多様な物でケツを綺麗にしていたというお話。フキの語源はケツを拭くからとか知らなかったそんなの… 葉っぱに藁に縄に木っ端、本当に日本人は多様なものでケツ拭きしてたんだなぁと感心する反面、ウルシの木でケツ拭いた話は引きました。結局ケツがかぶれてんじゃねーか!って思わず突っ込みました。2018/05/15