内容説明
カネなし!技術なし!市場なし!ピンチがいつも救ってくれた―。つぶれかけた酒蔵が、世界20カ国に展開するまでの七転び八起き。
目次
第1章 「負け組」の悲哀を忘れない
第2章 大失敗から学ぶ
第3章 捨てる勇気を持つ
第4章 「できること」と「やるべきこと」をはき違えない
第5章 常識や慣習にとらわれない
第6章 伝統が持つ奥深さを侮らない
第7章 発信しなければ伝わらない
第8章 打席に立ったからには、思い切りバットを振る
著者等紹介
桜井博志[サクライヒロシ]
旭酒造株式会社代表取締役社長。1950年、山口県周東町(現岩国市)生まれ。家業である旭酒造は、江戸時代の1770年創業。1973年に松山商科大学(現松山大学)を卒業後、西宮酒造(現日本盛)での修業を経て76年に旭酒造に入社したが、酒造りの方向性や経営をめぐって先代である父と対立して退社。79年に石材卸業の櫻井商事を設立。父の急逝を受けて84年に家業に戻り、純米大吟醸「獺祭」の開発を軸に経営再建をはかる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サンダーバード@怪しいグルメ探検隊・隊鳥
116
「獺祭」今ではすっかり有名になった地酒のブランドですが、その影にはこんな苦労があったとは。桜井社長が跡をついだ時は生産高は僅か700石。明日にも倒産し、自分の生命保険の額を考える毎日だったそうです。逆境をチャンスに変える発想と行動力が素晴らしい。地元では戦えないから東京で勝負。杜氏がいないから従業員で酒作り。普通酒では採算が取れないから敢えて高級な純米吟醸酒のみとする等々。「普通」であることを捨てる、なかなかできる事ではありません。企業再生の小説も多数ありますが、やはり本物はそれ以上でした。★★★★2014/02/26
メタボン
29
☆☆☆☆ 私の日本酒に対する概念を変えたのは「十四代」と「獺祭」だった。十四代はプレミアムがついてほとんど飲むことが出来ないが、獺祭は変わらず手ごろな値段で楽しめる。ただ一時に比べて手に入りにくくはなってきた。今年中には本蔵が完成するだろうから、そのときには年間通じて安定して飲むことが出来るのだろう。「磨き、その先へ」が「普通酒」として売られているとは知らなかった。もっとも3万円もする酒を自ら購入して飲むことはないだろうが。海外の人にも日本酒の美味しさをわかってもらいたいという獺祭のポリシーに共感する。2015/01/27
珈琲は深煎りで
26
どうせ沈みかけた船なのだから、思い切ってリスクをとった行動をしよう。純米大吟醸酒の製造一本に絞った逆境経営が、獺祭を生み出した。とりあえず、獺祭を飲まにゃ始まらないなぁ。こりゃあよくできた書籍兼広告だ。2014/10/31
T K
23
獺祭が呑みたくなる。負け組から世界へ。絞る捨てるとぶれないがハッキリしている。遠心分離機、四季醸造、勘を数値化、少し愛して長〜く愛して…2016/04/23
kakoboo
17
行きつけの飲み屋にはたくさんの銘柄の日本酒が置いてある。 そんな中他の銘柄よりも少しお高めながらにも、久世光彦や向田邦子にはまっていたころにこの銘柄をワイングラスでいただいたときに、「これは!」と叫んでしまったのが獺祭との出会いでした。 なかなか頂く機会はないですが、試験合格のお祝いにはその先にをぜひとも買いたいところです。本の趣旨とは全然関係ないことばかり書いてしまいましたが、中小企業の経営者である父に読んでもらおうと思いました。鋭すぎる視点が満載でスパークしますよ。獺祭スパークリングもおいしいです。2015/02/11
-
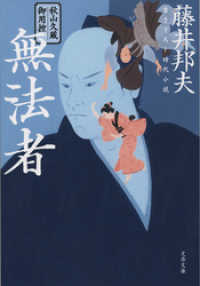
- 電子書籍
- 秋山久蔵御用控 無法者 文春文庫
-

- 文具・雑貨・特選品
- 演劇博物館94





