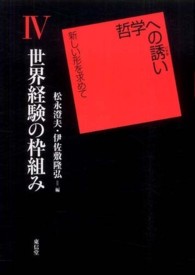出版社内容情報
100年前に日本を襲ったスペイン風邪は感染者数2千万人以上、死者は45万人とも言われる。芥川・与謝野晶子・荷風・志賀直哉・谷崎…新型コロナの出口が見えない今、あらためて文豪たちが描いた現実から学ぶものがあるのではないか。文庫オリジナル・文学アンソロジー。(解説・岩田健太郎)
内容説明
100年前、日本の文豪たちは20世紀最大の感染症・スペイン風邪に直面していた―。病に暴された芥川龍之介は辞世の句を詠み、菊池寛はマスクを憎悪し、与謝野晶子はソーシャルディスタンスを訴える!?現況と重なる感染症の記録を日記から小説まで収録。
目次
書簡(芥川龍之介)
「秋田雨雀日記」より(秋田雨雀)
感冒の床から(与謝野晶子)
死の恐怖(与謝野晶子)
「つゆじも」より(斎藤茂吉)
「断腸亭日乗」より(永井荷風)
十一月三日午後の事(志賀直哉)
流行感冒(志賀直哉)
途上(谷崎潤一郎)
神の如く弱し(菊池/寛)
マスク(菊池寛)
伸子(宮本百合子)
嚔「女婿」より(佐々木邦)
風邪一束(岸田國士)
著者等紹介
永江朗[ナガエアキラ]
1958年北海道生まれ。フリーライター。書店勤務の後、「宝島」などの編集に携わる。コラム、インタビューなど広い分野の執筆で活躍し、書評も信望が厚い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
シナモン
148
約100年前に大流行したスペイン風邪を題材にした文豪たちのアンソロジー。子供の感染に神経質になる親、結婚式当日に発病してしまった令嬢、マスクをめぐる心の有り様、細かく描かれた病状などフィクション、ノンフィクションありの内容で当時の世の中の様子がよく分かり興味深かった。凄さは分かっていても普段なかなか接することがない文豪たちの文章に触れるという意味でも読んで良かった。難しいかなと思ったけど解説もついているので読みやすかったです。2021/08/19
さつき
69
芥川龍之介の書簡、与謝野晶子の新聞寄稿文、永井荷風の日記など様々な形式の文章のアンソロジー。文豪達がスペイン風邪流行をどう見て過ごしていたかよくわかります。予防接種をしたりマスクをしたり人通りの多いイベントを自粛したりコロナ禍そっくりの行動に親近感を覚え、100年経っても人の行動は何も変わらないんだなぁと思いました。中でも志賀直哉の自伝的小説が面白くて収穫でした。歯切れの良い文章でスペイン風邪にまつわる悲喜こもごもが描かれていて、感染症の予防に対する人との温度差など今読むと身につまされる事ばかり。2023/09/03
吉田あや
67
100年前、世界中に広がったスペイン風邪。世界で4000万人、日本でも38万から45万の命を奪う程その感冒は猖獗していた。文豪たちの褥中日記や小説を集成したこのアンソロジーを読むと現在のコロナと同じような状態であり、衛生環境の著しい改善はあれど、政府の対応も未知のウイルスとの戦い方や予防方法も、何も教訓にできていないに等しく感じられる程に過去の経験は生かされていない。本書では感冒がいかにして100年前の人たちに広がり、どのように終息し、たった100年の後に(⇒)2023/08/22
shikashika555
53
Twitterで流れてきた表紙に興味をひかれて購入。 文豪の罹患した感染症や死因についての本かと思っていたら、大正時代に流行ったスペイン風邪に題材をとった短編や書簡や日記をまとめているアンソロジーであった。 罹患した際の症状の経過や心持ち、看護や治療についての言及、罹患を恐れるがための行動、政府の無策に対する批判などの記述が 100年経っても変わらぬものであると感じた。 菊池寛の「マスク」に出てくる医師の診断に刮目。聴診だけでたちまち弁膜症と右心肥大を言い当てて 治療法は「脂肪を食わず魚を食せ」と🙄2021/08/14
里季
41
1918年ごろから世界中に広まったスペイン風邪を、文豪たちはどう書いたかを検証する。何篇かあるうち、志賀直哉の「流行感冒」は、NHKでもドラマ化され、面白く読んだ。今の新型コロナ感染症にも通ずる時の文豪たちのの感染症に対する処し方がわかり、興味深かった。2021/10/14