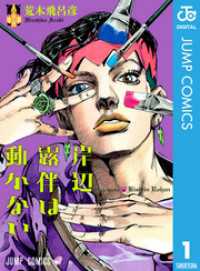出版社内容情報
アジア太平洋戦争は,アジアの民衆を戦禍にまきこんだだけでなく,民衆の財産を奪い,物資を収奪する過程であった.本書は日本軍支配下で展開された経済破壊と物資収奪のカラクリ,そのテコとなった軍票の実態,そして徴発や強制労働の諸相を通史的・総合的に分析する.戦後責任また戦後補償を考えるとき,まず参照すべき必読書といえよう.
内容説明
「大東亜共栄圏」とは、植民地や占領地の富と資源をすべて日本の戦争目的のために動員するという体制にほかならなかった。しかも日本軍の現地自活主義はさらに物資収奪を乱暴なものとした。本書は、日中戦争前後から敗戦まで日本の軍事支配地域で展開された政策と実態を総合的に分析する。戦後責任また戦後補償を考えるための必読書。
目次
序章 軍票被害調査の旅へ
1 中国戦線の物資争奪戦
2 南方軍政とはどのようなものだったか
3 「大東亜共栄圏」の実像
4 戦後処理をめぐって
終章 ふたたび被害調査の旅へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
寝落ち6段
13
日本軍が占領した際に発行した「軍票」という貨幣政策。占領先では物資を調達するために発行された。しかし、そのために大量にばらまかれた軍票は、各地でインフレーションを起こした。この太平洋戦争が人的、物資的な破壊だけではなく、軍票をめぐる経済的な破壊をも引き起こしたことがわかる。そこには、ヨーロッパ植民地からの解放という大義名分も霞んでしまうほど、その地を支配しようという暴戻な思惑が見えてくる。2020/10/27
CCC
12
軍票のことが気になったので読んだ。やはりそれぞれの事情を考えずやみくもに無理やり使う、使わせる形を取ったのが、現地の経済を破壊した最大の理由なのだろう。日本軍影響下にあったアジアでは日本から遠い地域ほど強いインフレに見舞われた、となにか別の本で読んだ憶えがあるけれど、物価指数のデータでその確認もできた。中国では国民政府の法幣というライバルがいたため競争が起こり、価格維持に一応の努力が払われたが、東南アジアではそれがなかったためにフォローがなかった、というのはちょっと興味深い。2022/04/21
isao_key
8
大東亜戦争時アジアの国々で日本軍が発行した大量の軍票。アジア諸国で日本軍の取った行動または残された軍票をめぐって戦後補償とは何かを考えさせる。特に甚大な被害を受けていたのが香港。強制移住のために占領当初150万人だった人口が1943年10月で98万人に減った。また海南島での鉄道工事のための労働者として2万505名が運ばれた。さらに1945年8月までに発行されたすべての軍票を合計すると6400億8864万円になったという。終章の被害調査は日本がアジア諸国に痛みを与えたことを知っておかなければならない話。2013/11/23
千本通り
6
今から30年以上前の本だが、大東亜共栄圏についてより突っ込んだ内容が描かれていて、今でも役立つ。大きく分けて第一章が中国戦線の物資争奪戦における通貨の戦い、第二章が南方軍政とはどのようなものであったか、第三章が大東亜共栄圏の実像、第四章が戦後処理についてである。 第一章は通貨の戦いで国民党の通貨「法幣(ほうへい)」に対して、日本軍の軍票や汪兆銘南京政府の「儲備(ちょび)券」は全然広まらなかった。理由は法幣のバックには欧米の大手銀行の協力があって信用力で圧倒していたからだ。 2025/08/09
dogu
5
アジア・太平洋戦中、日本軍占領下のアジアを語る上で基本となる本。軍政の実態やインフレの酷さ、インフレの害を現地と住民に押し付ける身勝手さが分かる。外地で日本軍が支払いに使ったのは「圓」と通称されていても軍票に過ぎなかった。日本円への両替は軍の許可制であり、軍人以外は制限されていた。2018/01/31