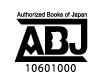特価¥1,100( 本体 ¥1,000 )
通常価格¥2,200( 本体 ¥2,000 )
蝉しぐれそそぐ!Kinoppy 電子書籍・電子洋書 全点ポイント25倍キャンペーン(~8/3)
商品詳細
日本刀は、「上古刀」「古刀」「新刀」「新々刀」「現代刀」と大きな変節を経て、一千有余年の歴史を刻んでいます。刀工数は古刀だけでも1万5千人。現代刀まで含めると10万人以上が切磋琢磨を繰り返して、日本刀を世界に誇る工芸美術品の域に高めてきました。
中世、大和国(奈良県)、山城国(京都府南部)、備前国(岡山県東南部)、相模国(神奈川県)、美濃国(岐阜県南部)の5箇所(「五箇伝」といいます)をはじめ産地ごとに特色が生まれ、江戸時代には江戸や大坂といった大都市や大城下町で諸藩の御抱え工が活躍。そうした刀工・刀剣史で大きな役割を担ってきた刀工は、約500~600工といわれています。
本書では刀工が活動した時代を検証し、各流派の興隆・隆盛・消長をビジュアル化しました。収載したのは約500工。初の試みとして在世年表の形で産地ごとに、刀工の活動期をマーキングすることで、刀剣・刀工史そのものを大きく俯瞰しました。主要流派である五箇伝の解説なども合わせて読むと、刀剣史の大まかな流れを把握できます。本書を紐解けば、各時代に活躍した刀工たちの息づかいが感じられるはずです。
◎刀剣・刀工在世年表
・平安時代の刀工 作刀中心地は大和・山城・備前・伯耆・九州諸国
・鎌倉時代の刀工 異流派の切磋琢磨で日本刀黄金時代が出来した
・室町時代の刀工 世情の混乱によって塗り替えられた“刀剣地図”
・安土桃山時代の刀工 「古刀」から「新刀」へと移り変わる重要な過渡期
・江戸時代の刀工 江戸後期、不世出の天才たちが新々刀の時代を拓く
・明治・大正時代の刀工 千年の技術を現代につないだ明治刀剣界の光明
◎五箇伝各派と刀工たち
・大和伝 大寺院の庇護を受けて発展し、美濃伝の礎を築く
・山城伝 日本刀を芸術の域にまで高めた山城工
・備前伝 全刀工数の4分の1以上を占める刀剣王国
・相州伝 天才・正宗が相州伝を大成し、鍛法が全国を席巻
・美濃伝 五箇伝最後発だが、戦国時代の需要を背景に大躍進
◎刀剣・刀工便覧
・『享保名物帳』収載名物一覧
・「十干十二支」順位表と二十四節気
・中・近世の不定時法と十二方位
・都道府県対照 旧国配置図
◎コラム
・平安・鎌倉時代の奥州鍛冶 平泉を拠点に奥州鍛冶の中心となった舞草鍛冶
・足利幕府を支えた遣明貿易 室町時代に数十万本の日本刀が輸出された
・著名工の拠点江戸鍛刀地図 御抱工は下屋敷、自由鍛冶は日本橋以北で鍛刀
・唯一の女性刀匠 大月源 筑前信国の助言により技に開眼した “女国重”
中世、大和国(奈良県)、山城国(京都府南部)、備前国(岡山県東南部)、相模国(神奈川県)、美濃国(岐阜県南部)の5箇所(「五箇伝」といいます)をはじめ産地ごとに特色が生まれ、江戸時代には江戸や大坂といった大都市や大城下町で諸藩の御抱え工が活躍。そうした刀工・刀剣史で大きな役割を担ってきた刀工は、約500~600工といわれています。
本書では刀工が活動した時代を検証し、各流派の興隆・隆盛・消長をビジュアル化しました。収載したのは約500工。初の試みとして在世年表の形で産地ごとに、刀工の活動期をマーキングすることで、刀剣・刀工史そのものを大きく俯瞰しました。主要流派である五箇伝の解説なども合わせて読むと、刀剣史の大まかな流れを把握できます。本書を紐解けば、各時代に活躍した刀工たちの息づかいが感じられるはずです。
◎刀剣・刀工在世年表
・平安時代の刀工 作刀中心地は大和・山城・備前・伯耆・九州諸国
・鎌倉時代の刀工 異流派の切磋琢磨で日本刀黄金時代が出来した
・室町時代の刀工 世情の混乱によって塗り替えられた“刀剣地図”
・安土桃山時代の刀工 「古刀」から「新刀」へと移り変わる重要な過渡期
・江戸時代の刀工 江戸後期、不世出の天才たちが新々刀の時代を拓く
・明治・大正時代の刀工 千年の技術を現代につないだ明治刀剣界の光明
◎五箇伝各派と刀工たち
・大和伝 大寺院の庇護を受けて発展し、美濃伝の礎を築く
・山城伝 日本刀を芸術の域にまで高めた山城工
・備前伝 全刀工数の4分の1以上を占める刀剣王国
・相州伝 天才・正宗が相州伝を大成し、鍛法が全国を席巻
・美濃伝 五箇伝最後発だが、戦国時代の需要を背景に大躍進
◎刀剣・刀工便覧
・『享保名物帳』収載名物一覧
・「十干十二支」順位表と二十四節気
・中・近世の不定時法と十二方位
・都道府県対照 旧国配置図
◎コラム
・平安・鎌倉時代の奥州鍛冶 平泉を拠点に奥州鍛冶の中心となった舞草鍛冶
・足利幕府を支えた遣明貿易 室町時代に数十万本の日本刀が輸出された
・著名工の拠点江戸鍛刀地図 御抱工は下屋敷、自由鍛冶は日本橋以北で鍛刀
・唯一の女性刀匠 大月源 筑前信国の助言により技に開眼した “女国重”
購入前の注意点
・3Dセキュア導入とクレジットカードによるお支払いについて
・この書籍はKinoppy for iOS、Kinoppy for Android、Kinoppy for Windows または Kinoppy for Mac(いずれも最新版)でお読みください。
・この商品は "Reader™" ではお読み頂けません。
・電子書籍は会員サービス利用規約に則してご利用いただきます。
・海外会員様にはプレゼントを贈れません。
・この書籍はKinoppy for iOS、Kinoppy for Android、Kinoppy for Windows または Kinoppy for Mac(いずれも最新版)でお読みください。
・この商品は "Reader™" ではお読み頂けません。
・電子書籍は会員サービス利用規約に則してご利用いただきます。
・海外会員様にはプレゼントを贈れません。