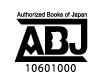特価¥1,375( 本体 ¥1,250 )
通常価格¥2,750( 本体 ¥2,500 )
蝉しぐれそそぐ!Kinoppy 電子書籍・電子洋書 全点ポイント25倍キャンペーン(~8/3)
商品詳細
19世紀後半以降、数学は「科学」から離れて独自の道を歩む傾向が強かったが、近年、他分野との連携によって数学自身の学問的発展が促されるケースが増えた。また、コンピュータの進歩による計算能力の飛躍的発展により、数学を「自然・社会現象を記述する『道具』」「自然や社会を正確に述べる共通『言語』」として利用するための教育を充実させ、より広く普及させるという要求が強まっている。
本書では、大学レベルの数学に関して、特に道具、言語としての数学を身につけるうえで必須のポイントを押さえつつ、著者の長年の教育経験を踏まえて、その意義と役割を詳述する。数学があまり得意でない人、あるいは数学は難しい言葉を使うから嫌いだという人、何に役立つのかわからないから勉強をする気になれないと思う人に読んでいただきたい。
1.始めに
2.言葉の重要性
3.数学が分かるとはどういうことか:無作法の勧め
4.数学のお作法
5.無作法のお作法:近似,精度,誤差,アルゴリズム
6.統計現象の取扱い:バラついた値と集団の性質
7.歴史から学ぶ証明の重要性
8.数学は役に立たない?
あとがき―無作法の勧め―
本書では、大学レベルの数学に関して、特に道具、言語としての数学を身につけるうえで必須のポイントを押さえつつ、著者の長年の教育経験を踏まえて、その意義と役割を詳述する。数学があまり得意でない人、あるいは数学は難しい言葉を使うから嫌いだという人、何に役立つのかわからないから勉強をする気になれないと思う人に読んでいただきたい。
1.始めに
2.言葉の重要性
3.数学が分かるとはどういうことか:無作法の勧め
4.数学のお作法
5.無作法のお作法:近似,精度,誤差,アルゴリズム
6.統計現象の取扱い:バラついた値と集団の性質
7.歴史から学ぶ証明の重要性
8.数学は役に立たない?
あとがき―無作法の勧め―
購入前の注意点
・3Dセキュア導入とクレジットカードによるお支払いについて
・この書籍はKinoppy for iOS、Kinoppy for Android、Kinoppy for Windows または Kinoppy for Mac(いずれも最新版)でお読みください。
・この商品は "Reader™" ではお読み頂けません。
・電子書籍は会員サービス利用規約に則してご利用いただきます。
・海外会員様にはプレゼントを贈れません。
・この書籍はKinoppy for iOS、Kinoppy for Android、Kinoppy for Windows または Kinoppy for Mac(いずれも最新版)でお読みください。
・この商品は "Reader™" ではお読み頂けません。
・電子書籍は会員サービス利用規約に則してご利用いただきます。
・海外会員様にはプレゼントを贈れません。
著者情報
藤原毅夫[フジワラタケオ]
1944年仙台に生まれる。父親の勤務の都合で日本全国いくつかの都市での生活を経験。10歳以降は東京で育つ。東京大学工学部助手、筑波大学物質工学系助教授、東京大学工学部助教授、教授、東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻教授を経て、2007年3月定年により退職。2007‐2017年東京大学大学総合教育研究センター特任教授。2017年より東京大学数理科学研究科特任教授(数理・情報教育センター研究センター)。工学博士、東京大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
1944年仙台に生まれる。父親の勤務の都合で日本全国いくつかの都市での生活を経験。10歳以降は東京で育つ。東京大学工学部助手、筑波大学物質工学系助教授、東京大学工学部助教授、教授、東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻教授を経て、2007年3月定年により退職。2007‐2017年東京大学大学総合教育研究センター特任教授。2017年より東京大学数理科学研究科特任教授(数理・情報教育センター研究センター)。工学博士、東京大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)