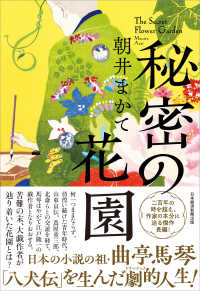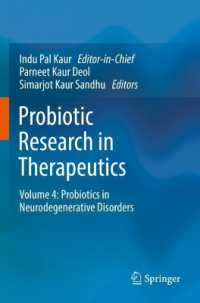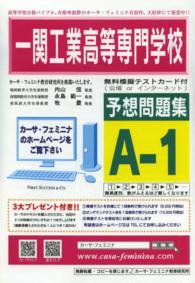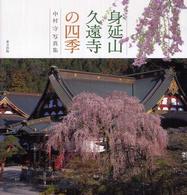内容説明
パンデミックはどうやって終焉するのだろうか?この新型コロナウイルスは、今後どうなっていくのだろう?これは誰もが今切実に知りたいことだろう。その答えは、本書の提言に従う人がどれほどいるかにかかっている。本書は、新型コロナウイルスの感染率を下げる方法及び、感染者の死亡率を下げる方法を提案するものである。
目次
まえがき パンデミックがやってきた
第1章 敵を知る
第2章 新型コロナウイルスの何が怖いのか?
第3章 新型コロナウイルスの防衛対策
第4章 新型コロナウイルスの診断
第5章 死なないための知恵
第6章 診断と処方
あとがき 読者の皆様へ―平和な日々が戻ることを願って
著者等紹介
刈谷真爾[カリヤシンジ]
医学博士、高知大学医学部附属病院病院教授。日本予防医学会評議員。高知県出身。東京工業大学工学部経営工学科卒、高知医科大学医学部卒、同大大学院医学研究科博士課程修了。高知大学教育研究部医療科学系臨床医学部門教授。放射線治療専門医としてがん治療に携わるかたわら、健康・予防医学にも精通しており、精神・食・運動のバランスを重視した健康生活を自ら実践し、その普及にも力を注いでいる。家庭では5人の子供の父親(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
チャー
7
収束の様子が見えず、今後の生活様式の実践に悩む中、対応のヒントになればと手に取る。本書では執筆時点で知られている情報を整理して、どのように対応すべきかを著者の視点から述べている。マスクや手洗いの効果等、具体的に記されておりわかりやすい。 一方で、感染者数と死者数にも言及しており、死因とするまでの経緯や、基礎疾患、合併後の影響も無視できないと著者は述べる。メディアで知る数字が、自身にリスクとして迫る数字かを考える良い視点であると感じた。良い方向に対応するためには、一人一人の正しい理解と適切な行動が必要。2020/08/09
ぶ~よん
3
誰が正しいのか未だによく分からないんだけど、何冊か読めば統計的な答えが出てくるだろう。この本は一年前に書かれたもので、ある程度答え合わせが出来た。著者の主張は、コロナはインフルエンザよりも若干ヤバいウイルスだけど、致死率は大したこと無いから、経済は動かした方が良いよ。ただ、高齢者と基礎疾患持ってる人は重症化しやすいし、重症者が増えると医療崩壊するから、皆で協力してマスクと手洗いはしようね。コロナに怯えてる人は、先ず生活習慣病を何とかしなさい。といったところで、世間の風潮とまぁまぁ合致してるかなと感じた。2021/04/04
NOK
2
マスメディアが発表する「数字」は、そっくりそのまま受け取ってはいけない。冷静で正確な情報をなぜ発信しないのだろうか。テレビ、新聞、ネットニュースだけで判断してはいけない。筆者の主張は冷静でわかりやすい。結局、普段から健康でいることが一番。あーだこーだ騒ぐだけ騒ぐ自粛警察の皆さんも、これを機会に、ご自身の健康を見直しませんか?運動しましょう。よく寝ましょう。健康な食事法を試しましょう。ストレスためずにいきましょう。いわゆる生活習慣病が、新コロは大好物みたいですよ。2021/01/04
uchi
1
4月30日に発売された本。今ではすでに常識になっているものも多かったです。2020/10/11
Shinjuro Ogino
1
前書きにある最新データが2020/4/7でやや古い。そのためか現在からみるとやや楽観的な見方で違和感がある。 本の後半約100頁は、ウイルスに負けないための一般的な運動、食事等の対策(著者のかねての持論か)の説明。 知らなかったのは、アブラナ科の野菜に含まれるスルフォルファンという栄養素の効果。ブロッコリー(特にその芽)、キャベツ等に含まれるという。 それから肝臓への負荷を抑えるため、1日の食事を取る時間を9時間以内に抑えるのがいいという(10時間経つと肝臓は新しい消化酵素を分泌する必要がある)。2020/06/08