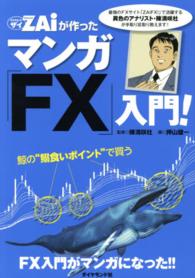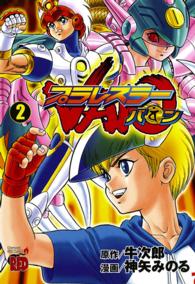内容説明
1920年代アメリカから始まった大量生産・大量消費は、人々の欲望を喚起した。だがやがてその欲望は我々の生活を隅々まで支配し、統御困難な状況に陥れた。その行き着いた果てが「自己の分裂」ではないだろうか?戦後日本消費社会のモデルとなった50年代アメリカ、高度消費社会の到来といわれた80年代日本、現代的な現象としてのケータイ、90年代末に台頭するガングロギャルまで…流行や価値観の変化から、それを規定する社会構造や政治体制までを考察する。
目次
1 消費とアイデンティティ―さまよう「自分らしさ」
2 ケータイとコミュニケーション―階層化と世界の縮小
3 消費と都市空間―八〇年代渋谷論への疑問
4 消費社会の音楽―ユーミンとアメリカ
5 政治と消費―ニューヨーク万博のイデオロギー
6 冷戦と博覧会―イームズがデザインしたアメリカ
著者等紹介
三浦展[ミウラアツシ]
1958年新潟県生まれ。一橋大学卒業後、(株)パルコ入社。マーケティング情報誌「アクロス」編集長を務める。90年三菱総合研究所入社。99年シンクタンク「カルチャースタディーズ研究所」を設立。消費社会研究家、マーケティング・アナリストとして活躍中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
魚京童!
12
自分で立つことができないから支えあって生きている。それが人なのだ。そういうことなんだと思う。消費社会に支えられようと思って気づいたら搾取されている。こうすれば不安がなくなります。お酒かな?こうすれば強い私でいられます。お酒かな?不安な世界で一人で生きていくことができなければ、二人でも支えられない。誰かがそんなことを言っていたけど、一人でいきていけないから二人で生きていくのだろう。野球選手ってすごいよね。バッターボックスに立ったら一人なのだ。ピッチャーも一人だけど、あとは味方がなんとかしてくれるって思えるの2023/03/21
Humbaba
6
時代によって移り変わるものだからこそ流行である.そして,それに従って価値観というものも変わりゆく.社会が拡大を続けるという,大量生産・大量消費の果てに,我々はどのような社会を築くのだろうか.2010/12/20
逸
1
消費社会の先頭にいたと思われるひとが見た日本と若者。面白いな、と思ったのが三章の80年代カルチャーについて、と、あと『趣都の誕生』の著者との対談。万博の話とかもうすこし調べたいなあ。2009/07/23
caca
0
隙間時間にパラパラ興味あるところだけ読み。 「自分らしさ」のテーマは、心の中のもやもやしていた部分が、なるほど、そんな考え方もあるのか。と思った反面、また何か分からないが違ったもやもやが出てきた気分。2017/04/22
miki
0
★★☆☆☆2014/04/17
-
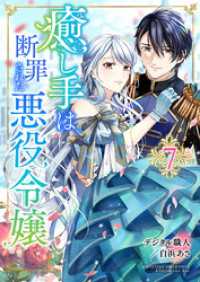
- 電子書籍
- 癒し手は断罪された悪役令嬢 7話 eb…