内容説明
日本の伝統美は、職人の技に支えられ、練りあげられてきた。大スペクタクルの動感や、金殿玉楼の圧倒的色彩を生みだし、ときには役者の命をあずかる歌舞伎の大道具方。その技術と洗練を、猿之助歌舞伎などを手掛け、つねに歌舞伎の先端を歩んできた舞台装置家が語る、裏方ならではの歌舞伎大道具の全て。
目次
第1章 大道具の子役(お師匠様これからお願いいたします;大道具の講義 ほか)
第2章 道具方岩をちぎって鼻をかみ(舞台空間を創る;舞台の定式 ほか)
第3章 大仕掛にてご覧に入れます(芝居をする大道具;「義経千本桜」の仕掛け ほか)
第4章 絶滅した舞台の復活(大ゼリ昔ばなし;口伝「青砥稿花紅彩画」 ほか)
著者等紹介
釘町久磨次[クギマチクマジ]
舞台装置家。明治39年佐賀県伊万里市生れ。十歳のとき大道具の十四代長谷川勘兵衛に弟子入り。大正13年金井大道具の背景画の責任者となる。記録として描き続けた舞台装置の原画(道具帳)は五千枚を超えた。国立劇場開場にさいし背景主任として参加。国立劇場、歌舞伎座、新橋演舞場、南座、東宝劇場など多数の舞台を担当した。長谷川伸賞受賞。勲四等瑞宝章受章。伝統文化ポーラ賞受賞。平成8年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
sawa
4
☆☆☆☆ 團菊佐全盛期に弟子入りし、それからずっと歌舞伎の大道具を手掛けている著者の話は大変貴重。歌舞伎といえば保守的なイメージがあるが、時代に合わせて大道具も数々の工夫がされているそう。役者の体格に合わせて襖の勾配を変えたり、誰の住居かによって、同じ鼠壁でも微妙に色を変えたり、そんなところまでと驚く。ずっと気になっていた「義経千本桜」の「四ノ切」の仕掛けを知ることができたのが、とってもよかった。2010/11/20
つばな
3
これすごい面白い!! 狐忠信の仕掛けは昔猿之助(現・猿翁)が説明していたのを見たことがあったんだけども、大道具側からの視線で見るとまた違う苦労があって面白い。音羽屋型だけでなくて、上方や新劇の手法も勉強した上での筆者の工夫はすごい。大仕掛け以外の大道具もこれからは面白く見物したいと思います。2014/04/06
みつひめ
2
歌舞伎の大道具にまつわる話はもちろん、明治・大正・昭和の名優たちについてのエピソードもあって、興味深く読みました。また、大道具の「道具帳」がたくさん掲載されていて、よかったです。「白浪五人男」の通しが、明治座にたてこもった菊五郎劇団によって、戦後復活されたいきさつは、今まで知りませんでした。この時の復活上演がきっかけで、浜松屋や稲瀬川以外の場もしばしば上演されるようになったそうで、それには大道具師・釘町さんがいらしたことが大きいのだなぁと、大好きな演目だけに、釘町さんにお礼を申し上げたくなりました。2009/02/18
ねこのすず箱
1
十歳から大道具一筋の著者。十歳の時すきになったものは一生物だとは言いますが、きっと天職だったんだろうな。役者はそれで稽古しているから寸法や位置はいつもの通りが大切、その上役者ごとにいつもの通りがある、なんて話は、実際そうなんだろうけど大変……。物理的に難しくても舞台上なら役者はやってのけてるというのも、これぞ本物という感じがしました。古くから伝わるものも大事にしつつ、新しい機構も積極的に取り入れる姿は、仕事ができる人は、無闇に変化を厭ったりしないんだなあと。尺で示された舞台の話は、聞くだけでたのしいです。2024/08/30
RYOKO
1
とても面白かった!目の錯覚やトリックをつかった仕掛け、役者の命をあずかる昔のセリ(今は電動だそうです)、時代物、世話物、舞踊劇で描き分ける背景。。芝居とは、このようなお道具さんはじめさまざまな職人が支える文化だとつくづく感じました。歌舞伎初心者の私にはわからない演目や名前も出てきたので、詳しくなったらまた読み返したい一冊。2009/06/11
-
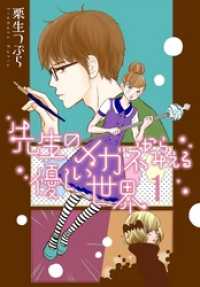
- 電子書籍
- 先生のメガネからみえる優しい世界【描き…








