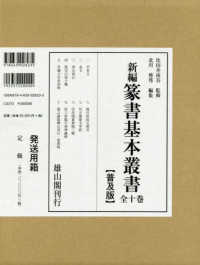出版社内容情報
八幡和郎[ヤワタカズオ]
著・文・その他
内容説明
いまや一般常識となっている47都道府県。地図を見ていると、県名と県庁所在地名が違う県や、各地域が独立しているように見える県など、不思議に感じる点が多々あるが、その背景には明治維新の激動で「消えた府県」の存在があった。公式記録に残っていない幻の県、設置1カ月で消えた県、県庁が半年ごとに変わった県、消滅を繰り返した県、飛び地だらけだった県など、都道府県にまつわる雑学をベストセラー作家が完全網羅。
目次
序章 なぜ、都道府県の数は47なのか―誤解だらけの廃藩置県
第1章 北海道・東北編―戊辰戦争の影響で誕生した「幻の県」の数々
第2章 関東編―県庁が日本橋にあった「品川県」、千葉にあった「葛飾県」
第3章 中部編―松本にあった「筑摩県」消滅の裏事情
第4章 近畿編―なぜ「彦根県」「姫路県」は存続しなかったのか
第5章 中国・四国編―地図から「香川県」「徳島県」が消えた時代
第6章 九州編―「佐賀県」「宮崎県」がいったん消滅した理由
著者等紹介
八幡和郎[ヤワタカズオ]
1951年、滋賀県大津市に生まれる。東京大学法学部を卒業後、通商産業省(現・経済産業省)に入省。北西アジア課長、大臣官房情報管理課長、国土庁長官官房参事官などを歴任。在職中にフランスの国立行政学院(ENA)に留学。現在は徳島文理大学大学院教授を務めるほか、作家、評論家として活躍中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Tadashi_N
やす
金吾
yoneyama
kabeo
-
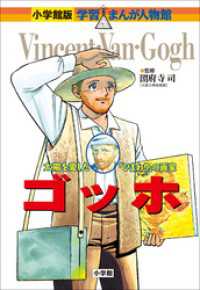
- 電子書籍
- 小学館版 学習まんが人物館 ゴッホ 小…