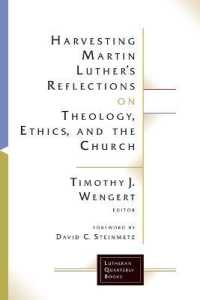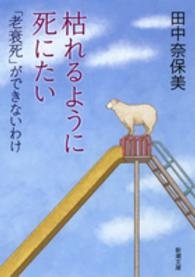内容説明
洞窟壁画から次世代型不揮発メモリまで進化の歴史で読み解く記憶デバイス技術。
目次
第1章 コンピュータ前史の記憶デバイス
第2章 コンピュータ黎明期の記憶デバイス
第3章 コンピュータの普及を支えた磁気記憶装置
第4章 光で情報を記録する記憶デバイス
第5章 半導体メモリの大容量化と多様化
第6章 最先端の記憶デバイスの技術と未来
著者等紹介
石川憲二[イシカワケンジ]
科学技術ジャーナリスト、作家、編集者。1958年東京生まれ。東京理科大学理学部卒業。週刊誌記者を経てフリーランスのライター&編集者に。書籍や雑誌記事の制作および小説の執筆を行っているほか、25年以上にわたって企業や研究機関を取材し、技術やビジネスに関する解説を書き続けている。扱ってきた科学技術領域は、電気・電子、機械、自動車、航空・宇宙、船舶、材料、化学、コンピュータ、通信、システム、ロボット、エネルギー、生産技術、知的財産など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
くら
2
こういう話大好き。人類が知恵を出して作り上げてきた技術の歴史、すばらしい。CDやDVD、BDのしくみや違いとか、わかりやすくてなるほど~って思った。さまざまなメディアの栄枯盛衰の要因なんかも興味深かった。2016/10/14
イガラシ
1
情報を残すということは遙か昔から行われており、記憶装置もそのうちの一つに過ぎない。洞窟の壁画、紙、フィルム、テープ、パンチカードなどを経て現在使われているハードディスクやフラッシュメモリ等にたどり着く。その途中で消えていったものも数多くあり、今後期待される技術もある。細かい技術的なことはあまりなく、それぞれの記憶装置の紹介が中心だった。2015/11/24
の
0
メモリ(記憶)の仕組みと歴史を図解したもの。条件ごとに最適なデバイスを探して来て、多種多様な記憶装置が生まれたと思うと感慨深い。1か0かで現象を説明して行くコンピュータは、古代のロープの結び目が有るか無いかで物事を表現するアプローチに似ており、パンチカードやディスクの記録方法の仕組みを読んでいると、アナログとデジタルの境目の感覚も曖昧になってくる。こうした勉強をしなければ毎日コンピュータやソフトを使っていても中身は分からないのは、それだけデジタルがアナログな生活浸透しているということか。2014/07/13
凡人君
0
はじめは歴史の本を読んでいるのではないかと錯覚する。アナログの記憶からデジタルの記憶に至るまで、今後の展望も含めて詳しく解説されている。説明自体がわかりやすいたとは思えないが、メモリの第一人者以外からは到底知ることができない内容が述べられた一冊。メモリの辞書として、役立つかもしれない。2014/04/06
isiko
0
図解がかなり分かりやすい2013/04/03