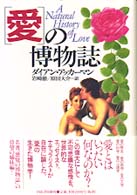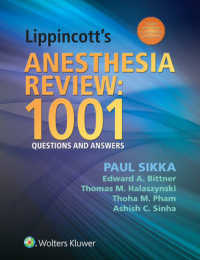内容説明
第一次世界大戦で、日本とドイツの両軍は中国の青島で激突、ドイツ軍が降伏して日本に多数のドイツ兵俘虜が送られることになる。会津出身の板東俘虜収容所所長・松江豊寿大佐は、陸軍上層部からの批判にもめげずに俘虜たちを人道的に扱い、彼らは自由に様々な活動を許された。その活動は、ベートーベンの『第九交響曲』の演奏に始まり、演劇発表会やサッカーなどのスポーツ、さらに近隣の人々にパンやチーズの作り方を教えたりと、地元民との交流を重ねた。「世界のどこに、マツエ大佐のようなラーゲル・コマンダー(俘虜収容所所長)がいたでしょうか」と、後にドイツ人俘虜たちに言わしめた会津の男・松江大佐とドイツ人俘虜たちの感動の物語。
目次
第1章 鳴門市ドイツ館
第2章 第一次世界大戦
第3章 板東俘虜収容所
第4章 人々とのふれあい
第5章 会津藩の人
第6章 ヴェルサイユ条約
第7章 第二次世界大戦
第8章 戦後の交流
著者等紹介
星亮一[ホシリョウイチ]
1935年、宮城県仙台市生まれ。東北大学文学部卒。日本大学大学院総合社会情報研究科修了。作家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Willie the Wildcat
45
収容所を通したドイツとの繋がり。施設内での生活と地元との交流。文化の醸成の根底に、所長である松江氏の人柄と哲学。写真などからも滲む自由。特に音楽の交流に言葉は要らないよなぁ・・・と、改めて音楽の良さを感じる。一方、松江氏に関する記述が限定的であり、加えて”会津”武士道との繋がりの論旨が、どうにも弱い気がする。戊辰戦争から第二次大戦の解説も簡潔・丁寧ではあるが、これまた主題との関連性が薄いという印象。ストレートに「坂東俘虜収容所」ってタイトルにした方がすっきりするのになぁ。2016/08/29
B.J.
3
●松江豊寿大佐 :グランドを作りサッカーやホッケーを楽しみ、近所の池にはヨットまで浮かべさせた。近隣の人々に牛の飼い方やチーズ・バター・パンの作り方を教え、石橋も作った・・・。独逸兵俘虜の幅広い活動。 ●「デイ・バラッケ」:俘虜収容所内新聞-自由な論調。 ●松江大佐の敗者の心を思いやる姿勢が、武士道に西洋の騎士道にも通じる広がりを与えた。 ⇒口癖であった「独逸人も国のために戦ったのだ」、という武士道的な敗者への思いやり。・・・本文より2020/03/05
くじら
0
恥ずかしながら、全く知らない歴史でした。こんなすばらしいことが戦時中の日本で起きていたなんて。日本人の誇りです。このような出来事や人物が、もっともっと無脚光を浴びるべきだと思います。2016/11/06
SS
0
実は再読。映画も見たけど冗長。でも、本作はいい意味。中村氏の「二つの山河」は、中編で素朴。読了して、昔行ったときは雨の中(お遍路さんに間違えられた)だったので、また往きたし とおもふ。 2013/02/15