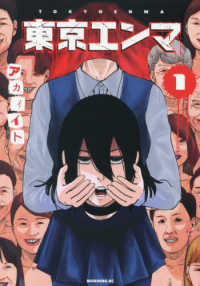内容説明
カフカ・コレクションの「ノート」は、作者自身が書いたときの姿に限りなく近い形で再現されている。したがって作品の成立過程がはっきりと見てとれる。読者は小説家カフカの秘密、未知の面白さを発見することができる。「ノート1」は、手稿の前半部分から16篇を収録。
著者等紹介
カフカ,フランツ[カフカ,フランツ][Kafka,Franz]
1883‐1924。チェコのプラハに生まれる(当時はオーストリア=ハンガリー帝国領)。両親ともドイツ系ユダヤ人。プラハ大学で法学を専攻。在学中に小説の習作を始める。卒業後は労働者傷害保険協会に勤めながら執筆にはげむ。若くして結核にかかり、41歳で死去。『変身』などわずかな作品をのぞき、そのほとんどは発表されることなくノートに残された。死後、友人マックス・ブロートの手により世に出され、ジョイス、プルーストとならび現代世界文学の最も重要な作家となっている
池内紀[イケウチオサム]
1940年、兵庫県姫路市生まれ。ドイツ文学者、エッセイスト(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
53
巻末の解説にある通り「工区分割方式」で建てられる城が『万里の長城』だ。『審判』が書かれた過程に当てはまるため、我々の知る中国にあるものではない。カフカの創作は中断が多く、断片として残っている。とすれば、この城とは代表作『城』を思わせ、彼の迷宮的な決して完成しない思考の象徴的な表現のことだと分かる。およそ答えなど出る見込みのない計画をつくり、それを遂行する官僚的な生活に自ら飛び込む。彼の人生をみると、途中で目的を見失うというよりも、最初から実現可能な目的は設定されていなかったようにみえる。2025/05/12
ぞしま
14
いくつもの(中断)という二文字が印象的だ。短篇として独立されて箇所もあったと気づいたり、本書は試作的断片とも読めるだろう。本人の意思は?と問われれば「焼いてくれ」とブロートに宛てた言が本心なのかどうなのかも分からないのだから推して(そして)思い込んで読むより仕様がない。中断がカフカの小説の魅力を形成しているのではないか?こんなことを言うと怒られてしまうだろうか。いつまでも辿り着けない城も終わりのない城壁の作成も、カフカの小説そのままじゃないかと思う。同時に魅力の一部でしかないとも。色々考えてしまう。良書。2019/01/17
王天上
6
「ある戦いの記録」の読んだことのないバージョンが収録されていて、これがとてもグッときました。短篇ではこの作品が一番好きだなあ。あとお父さんに死刑宣告されるやつとか。2013/07/13
Tonex
4
カフカ生前には発表されなかった短篇16篇を収録。もともとノートに手書きでぐしゃぐしゃと書かれたメモ書きや下書きのようなものだったはずなのに、活字に起こされてタイトルがつけられると、ちゃんとした一つの作品に見えてしまう。でも、本当はそういう完成品ではない。表題作「万里の長城」をはじめ「狩人グラフス」「こうのとり」など他の本で読んだことのある作品がいくつか収録されているが、それで完結していると思っていた作品が、実は執筆途中で中断されたものだったことを知って驚いた。2015/11/03
ちあき
4
マックス・ブロートの編集が加わらないバージョン(手稿版)にもとづいた池内訳の、真骨頂ともいえる巻。文章自体もそうだが、随所にあらわれる「中断」が読み手の意識に引っかかってくる。日本語におきかえられているのに、カフカがついさっきまで書いていたかのような感触もある。「工区分割方式」が記憶に残る表題作は、各段落を切りきざんで順序・回数に頓着せず何度も読みかえしていくとさらに味わい深いことを発見した。2009/10/22