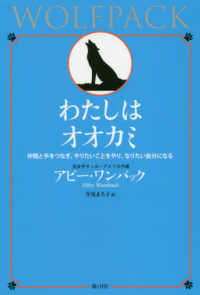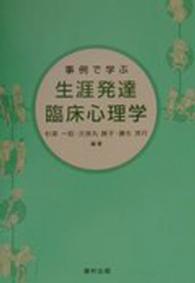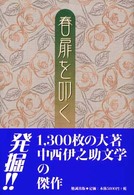出版社内容情報
ロシア・フォルマリズム時代、プラハ学派時代を経て、アメリカ亡命後のハーバード大学時代まで現代の詩学の礎をなすその業績の全貌。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
6
日常言語が芸術言語になる条件は何か? 著者は、創作や説得の側から芸術を捉える詩学から問う。フォルマリズムから出発した著者は、意味に対応する音声に留まる音韻論を音同士の関係(音素)に転換した。その際情報理論のビット単位を音素の対立的な弁別素性として言語学を構造的に体系化する。さらにその詩学を、作者と読者を送受信者とし、芸術言語を弁別素性の頻度や多様性において日常言語と区別した。が、古今の詩の読解にもかかわらず、それらシンメトリカルな音素関係が、読者の美や快感を享受する条件となりうるか?という議論を惹起する。2021/12/05
T. Tokunaga
5
正直なところ、ダンテ論、シェイクスピア論、ブレイク論くらいしか、語学の都合でよく理解できなかったのだけれど、文法的曖昧さに逃げる英米詩学より確実に有用な方法論を用いてはいる。ただ、そのフォークロアの口承的に整然とした文法的構造というのは、かなり精査が必要(フォークロアには採録者などの編集がつきものだし)で、また文法的な前提として、構造主義を用いているため、論理実証主義や日常言語学派からの見直しも必要であろう。歴史的方法論としては微妙な気がしている。組み合わせのひとつとしては使える。2025/01/08