出版社内容情報
イギリスを中心に、ヨーロッパ世紀末の抱えていた諸問題を、絵画・文学・音楽さらには性意識にわたる多様な動きの中に探る。
内容説明
19世紀末から今世紀初頭にかけての絵画・文学・音楽などひろい範囲にわたる芸術活動を、現代のそれと照合しながら考察し、世紀末的なるものに通底する美学を探求する。
目次
第1章 1900年の回想―ビアズリーと現代
第2章 アール・ヌーヴォーからアール・デコへ―コランの眼・ローランサンの眼
第3章 殺人未遂事件―世紀末へのタイムトンネル
第4章 芸術の構造と性の構造―オーデンの場合
第5章 普遍へ飛翔するエロス
第6章 ラファエル前派―世紀末耽美主義のルーツ
第7章 世紀末とルネサンス―ミケランジェロ解釈とペイター
第8章 世紀末とロマン主義―理想の挫折
第9章 黄色考現学―なぜイエロウなのか
第10章 2人のイゾルデ―ビアズリーとワーグナー
第11章 象徴の美学―絵画、音楽、そして文学
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
愁
2
19世紀末の芸術論といえば河村錠一郎氏。個人的にビアズリーにどハマりした時期があったが、関連文献でよく河村氏の名前を目にした。この本もビアズリーやイエローブックについてはもちろん、アールヌーボーからアールデコへの変換、ルネサンス、ロマン主義と当時の空気を感じられる「美学」の入門書。
おがわ
0
ビアズレーの装丁、世紀末美術となればそれだけで食らい付かざるを得ない。文学、音楽、絵画がジャンルを越境し、互いに連環を織りなしながら花開いた世紀末美術。/一つ一つの章はややまとまりに欠け読み辛さはあるものの、ワグナー、イエロウ・ブック、アール・デコと内容は充実。/とりわけあまり美術史上で高い評価を得ているとは言い難い(?)ラファエル前派をかなり詳細に論じている第6章は筆者自身の嗜好も読み取れて興味深く読んだ。(獄本のばらなんかはエッセイでラファエル前派を「キッチュ」と言い切っている)細部は執拗なまでの写実2021/11/09
志村真幸
0
できれば、前著『ビアズリーと世紀末』を読んでから、この本に進んだ方がいいと思う。 ビアズリー、アール・デコ、モリス、ラファエル前派、オーデン、ハヴロック・エリス、ペイター、ワイルドなど、イギリス中心にヨーロッパ各地の、19世紀後半から20世紀初頭のさまざまな文化的様相がとりあげられている。 いささかまとまりに欠けるのだが、ひとつの大きなテーマとなっているのは当時の男性同性愛。どんなひとたちがいて、どのような扱いを受けていたかがよくわかる。 総体として世紀末の雰囲気は伝わってくるのではないか。 2019/10/06
-
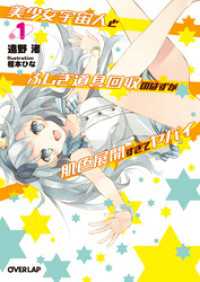
- 電子書籍
- 美少女宇宙人とふしぎ道具回収のはずが肌…




