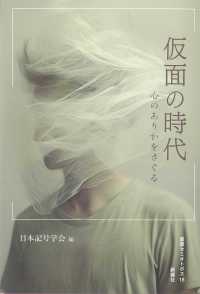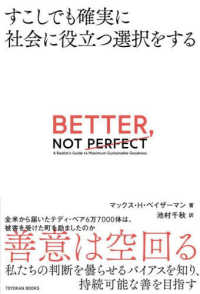内容説明
江戸城を不在にし「国事」に自ら奔走した慶喜は、歴代の中できわめて特殊な存在であった。では、将軍がそのように変質した契機はどこにあったのだろうか。そもそも、徳川将軍とはいったい何なのか。儀礼や伝統、先例や慣習といった事柄に着目したときに見えるものとは。伝統社会から近代へと転換する時代の中での家慶・家定・家茂らの実像とその苦闘とは。「権威の将軍」から「国事の将軍」への転換というあらたな視角を打ち立てる、画期的な幕末史研究。
目次
序 「権威の将軍」と「国事の将軍」
第1章 徳川将軍の権威と本流
第2章 十二代家慶と内憂外患の時代
第3章 十三代家定と開国日本
第4章 「国事の将軍」誕生―十四代家茂
第5章 果てしなき奔走
第6章 語られない十五代将軍
結語 徳川将軍という逆説
著者等紹介
久住真也[クスミシンヤ]
1970年生まれ、山梨県出身。茨城大学卒業後、中央大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(史学)。現在、中央大学人文科学研究所客員研究員および大学非常勤講師。専攻は日本近世・近代史、特に明治維新史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
バルジ
1
個人的には「権威の将軍」から「国事の将軍」へと変化せざるを得なくなった徳川将軍の役割が面白かった。 自己否定の論理を孕んだ文久改革とそれを主導した松平春嶽「政権」の役割はもっと重視されても良い。2018/11/03
ELW
1
大御所家斉に対する違った評価が新鮮だった。水戸一派が慶喜を14代将軍につけようとしたのはなかなかな失当。家茂が頑張ったのはよく分かったが、時代の趨勢と教養のせいかもしれないが、春嶽はじつは幕府を支える人材ではなかった のではないか。『ヴァロワ朝』を読んでおいてよかった。2018/08/24
アメヲトコ
1
幕末の徳川将軍は、それまでの「権威の将軍」から「国事の将軍」への質的な転換を遂げたのではないかという見通しにたち、そこでの将軍の苦闘を描いた一冊。とくに14代将軍家茂の劃期性に大きく光が当てられているのが面白いところで、著者自身の思い入れの深さもよく伝わってきます。2015/01/26
Teo
1
権威の絶頂だった家斉時代からあれよあれよと言う間にそれを失い、遂には倒れるに至るまでの幕末期の将軍のあり様を家斉→家慶→家定→家茂→慶喜と追っていく本。中学時代の知識では江戸幕府はぽっきりと折れる様に倒れたかの印象だったが、年を経るにつれ「色々あったのよ、色々」と言うのまで分かってもなかなか直感出来なかったのが、確かに凋落の速度は速いもののそれなりの順を追ったものだと言うのが分かる。まあ、清朝末期もこんな感じで、げに恐ろしきは西洋の圧力。2009/03/19
akuragitatata
0
徳川将軍家の権威低下と国事行為の遂行への変化という徳川将軍のあり方の変容から、幕末の将軍家を論じた一書。家茂の状況を重く見る視点はなかなか感慨深い。大政奉還にいたる委任論自体が家斉の頃からわき上がってきて、事実上遂行不可能な状態に陥り将軍家が権力基盤とその名分を失っていく過程は極めて説得力に富む。この本では論じられていないが、攘夷と委任に権威を与えていたのは孝明天皇だったとも言えるわけで、もし孝明天皇が生きていたら無血開城もなかったかもしれない。でも幕府の中も内紛状態だったしそんな簡単でもないかな。2017/08/23
-

- 和書
- 花のカメレオン