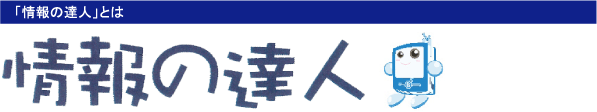 |
| 「情報の達人」は、「ビデオ(映像)」に加えて、「スライドショー」「テキスト」「ウェブ」の四つを、目的などに合わせ、自由に組み合わせてお使いいただける教材パッケージです。 ●ビデオ(総論) 総論(第0講)は、各巻のテーマについて、実写やアニメ、CGなどを駆使した映像でわかりやすく説明しています。図書館の講習会や授業の初回などに上映するのに適しています。上映時間は、各巻とも15分程度にしました。 ●ビデオ(各論) 各論(第1〜10講)は、各巻の内容を10回に分けて詳細に説明しています。各講の冒頭にはプロローグを置き、受講者の興味を引きつけたうえで、具体的な知識と技能の解説に移ります。また、最初に「ねらい」を、最後に「まとめ」を提示して、受講者の理解を助ける工夫をしています。図書館の講習会や授業の各回などに上映するのに適しています。上映時間は、各巻各講とも、5〜10分程度にしました。なお、順番に視聴するだけでなく、選択的に使うことも考慮し、映像中には「第○講」という表示は入れていません。 ●スライドショー ビデオ(総論・各論)の内容を口頭で説明するときに利用できる連続静止画です。プレゼンテーションソフトのように、説明者のペースで一枚一枚進めていくことができます。各巻各講とも約15枚とし、ビデオの内容を振り返るのにも、テキストの内容を詳しく解説するのにも使えます。 ●テキスト ビデオの内容について詳細・補足説明を行なった小冊子です。講習会や授業などにおけるビデオやスライド(口頭説明)との併用はもちろん、「読んでわかる」ように書かれているので、自習用の教材としても適しています。 ●ウェブ(インターネット) ビデオ、スライドショー、テキストなどと併せて利用できるさまざまな教材を当ウェブサイトに用意します。講習会や授業などで利用しやすいように、そのまま印刷・配布が可能な原稿などを順次、提供していきます。また、「情報の達人」の商品案内や活用レポートなどの最新情報を随時、掲載していきます。 |
| 「情報の達人」の特徴 (1) 情報リテラシーの「考え方」を重視 単なるハウツーものにならないように、情報リテラシーの「考え方」の習得を目標としました。例えば、個別のデータベースの検索画面を登場させ、実際の操作手順を提示するのではなく、データベースの利用に必要な「基本的な概念(理論)」の解説を行なっています。「考え方」を踏まえて、それぞれの図書館や授業などの状況にあわせて説明を行うことができます。 また、インターネット上のツールなどは変化が激しいため、映像化してもすぐに古くなってしまうことがあります。そうした事態を避け、教材として長く利用できるようにするためにも、ビデオ、スライドショー、テキストでは「考え方」の習得を重視しています。個別のツールなどについては、ウェブ教材のなかで取り上げていきます。 なお、「情報リテラシー」とは、単なるコンピュータの利用に留まるものではありません。図書・雑誌などまでを含めた「総合的な情報(メディア)の活用」の能力であるととらえています。メディアセンターとしての「図書館」を前面に押し出しているのもこのためです。また、「メタ認知」など、最近、重視されている事項を積極的に取り入れています。 (2) 段階的・体系的な学習に対応 第1巻は、大学における情報リテラシーの重要性を印象づけることに主眼を置いています。第2巻は、ゼミを例にしながら、さまざまな発表(プレゼンテーション)について、第3巻は、論文形式のレポートを取り上げながら、レポート・論文について、必要な知識・技能(情報リテラシー)の理解を進めることをめざしています。 第1巻は大学新入生、第2巻は大学2〜4年生、第3巻は大学2年生以上を主な対象として想定していますので、段階的な学習を進めることが可能です。ただし、いずれの巻も、平易な表現を心がけていますので、対象以外の学年あるいは高校生や社会人にも利用できるようになっています。 また、各巻は、「総論」でテーマの全体像を把握したうえで、サブテーマを「各論」で理解していくという構成になっており、体系的な学習が可能です。もちろん、目的に応じて、各論を選択的に取り上げることもできます。 (3)「わかりやすさ」を追究 いわゆるエデュテインメント的な要素を取り入れて、「楽しみながら」学べることを意図しました。比較的高度な内容を含んでいますが、表現は平易かつ親しみやすいものとなるように工夫しました。特にビデオ(映像)では、次のような方針で制作に臨みました。 ・ ほどよい「ストーリー」性(いわゆる「ドラマ」ではなく、かといって単調な「説明」でもない) ・ 実写だけでなく、アニメ、CGなどをさまざまな表現方法を駆使 ・ 重要な用語や聞き取りづらい用語(専門用語)には、テロップを表示 (ただし、煩雑にならない数に留め、スライド、テキスト、ウェブ教材でフォロー) ・ 携帯電話と図書を形象化したキャラクター「ブックルくん」を親しみやすい「舞台回し」役として採用 ・ 理解しやすさを重視して、学術的・専門的な用語(概念)について、必要に応じて日常語などによって説明 ・ 各論(第1〜10講)の冒頭に、興味喚起と問題提起のためのプロローグを挿入 |
|
「情報の達人」活用例 「情報の達人」は、図書館の講習会や授業などにおいて、目的や状況に応じて、ビデオ、スライドショー、テキスト、ウェブ教材を自由に組み合わせてお使いいただけます。活用例を挙げておきますのでご参考になさってください。 |
|
Copyright by KINOKUNIYA COMPANY LTD. |