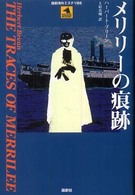内容説明
増田レポートが「どっこい生きている」地方にショックを広げている。このままでは地方は消滅するのか?否。どこよりも早く過疎化、超高齢化と切実に向き合ってきた農山村は、この難問を突破しつつある。現場をとことん歩いて回る研究者が丁寧にその事例を報告、地方消滅論が意図した狙いを喝破する。
目次
序章 「地方消滅論」の登場
第1章 農山村の実態―空洞化と消滅可能性
第2章 地域づくりの歴史と実践
第3章 地域づくりの諸相―中国山地の挑戦
第4章 今、現場には何が必要か―政策と対策の新展開
第5章 田園回帰前線―農山村移住の課題
終章 農山村再生の課題と展望
著者等紹介
小田切徳美[オダギリトクミ]
1959年生まれ。明治大学農学部教授。農政学・農村政策論・地域ガバナンス論。東京大学大学院農学研究科博士課程単位取得退学(農学博士)。(財)農政調査委員会専門調査員、高崎経済大学助教授、東京大学大学院助教授などを経て、現職。著書に『日本農業の中山間地帯問題』(農林統計協会。1996年日本農業経済学会奨励賞受賞)、『農山村再生に挑む―理論から実践まで』(編著、岩波書店。2014年地域農林経済学会特別賞受賞)など多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
43
「地方消滅」への反論という意味で、深く調査がなされており、説得力があった。各地で続々と地域を復興・発展させるための取り組みが行われ、参加する若者も少なくない。やはりデータだけを見、ネガティブな判断を下すより、現場を実際に歩いて見てみないといけないだろう。2015/04/21
壱萬参仟縁
42
Amazonで品切れに。急きょ地方都市にて購入。小田切教授はYouTubeでの講演で田園回帰現象の意義を強調されていた。本書もその論点は第Ⅴ章で力説されている。小田切先生の図式は知っていたが(27、69頁)、特に後者の図式を乗り越える策を提起されているのが心強い。165頁の図4-1の集落再生のプロセスがそれである。先生はV字型回復のようではなく、U字型のように寄り添い型・足し算の支援と、初めて事業導入型の掛け算の支援が独創的である。極めておススメできる新書。2014/12/21
けんとまん1007
38
自分自身、地方の都市の、どちらかというと農村地帯に暮らしている。数年前から、声高に言われている限界集落、地方の市町村の問題について、どこかきな臭い部分を感じていたので、この本にたどり着けてよかったと思う。もちろん、安穏としていられるわけではないが、人が暮らすということを中心にしているのが素晴らしい。地方云々、人口減の中で、相変わらずの論調が気になっていた。そこでいわれる成長戦略の文字は、旧態然の発想なのだろうと思っているからでもある。2017/01/08
Mark
30
地域活性化から地域づくりへの変遷を踏まえ、地域振興の内発性、総合性・多様性、革新性を明らかにし、地域づくりのフレームワーク、柱を説いている。特に中国山地を具体的な事例として紹介し、農村再生のフロンティアとして位置づけ、そこにある特色、課題を明確にしている。経済という視点だけでは容易に解決できない問題点が多数あることがよくわかる、一方で価値観というものをどのように形成していくかということが非常に難しい課題であることも認識。今後に希望が見いだせる本でした。2015/01/25
たばかる
28
2014年、増田レポートに対する反発の中の一冊。本書では行政と自治体の財政的な支援の問題が取り上げられる。予算や政策などによって地域復興が行政によって舵取られるため、必ずしも地域住民の意向が反映されず、彼らの主体的な参加意欲が薄れるとして現行の状況を批判する。そして成功している事例として山口市仁保地区、鳥取県智頭町や島根県邑南町などの人口の社会増を挙げる。これらの地域の町づくりと増加しつつあるいわゆるIターン•Jターンの「田園回帰」の傾向のマッチが人口回復の兆しになると期待していた。2021/05/04